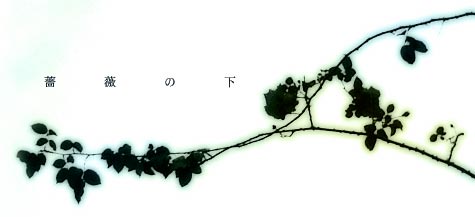
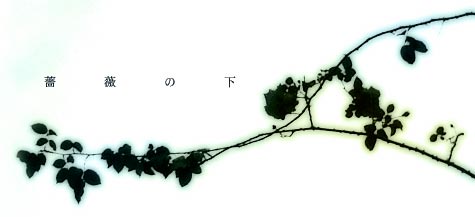
| 青年は止めていた息をそっと吐いた。その冷ややかな空気の流れに眼を細めた神父の額へと掌を当て、慈しむかのような動きで撫でる。 「熱が上がってるよ、神父さん」 「傷を負ったからな。大したこともない」 「人間は不便だな。命が儚な過ぎる」 「そうでもないさ……昼と夜とを生きることが出来る、その代償だよ」 青年の冷たく濡れた舌が唇を辿った。呼応するように薄く開いたそれに招き入れられ、エドワードは深く口付け熱の高い粘膜をゆったりと蹂躙する。 指腹で膚を辿り、布越しに下肢を撫でると微かに喉が鳴った。唇を解放すると大きく息が貪られ、瞼を閉じたその顔に薄く汗を乗せたロイは溢れ流れた唾液を拭う。その合間に下衣の留め具を外し滑り込ませた指で直接触れれば震えた足ががつ、と棺を軽く蹴るが咎められることはなくて、ただ金髪を掻き上げられた。 性急な仕草で下衣を抜き、片方だけ脱がせた長靴を放る。もう片方を抜くのが面倒で履かせたまま露わになった思うよりも細い足を撫で、膝裏に手を掛けて裸足の左脚だけを棺の上へと踵を突かせた。 「………なんだ、随分と余裕がないな」 「アンタが来るのが遅いのが悪い。……早くしないと夜が明ける。今夜は帰ってやらないと、アルが心配するからな」 言いながら、奥まった秘所を指で探れば微かに苦痛を示し眉が寄った。ああそうか、と呟いてエドワードは身を起こしシャツを探る。 「………なんだ、」 「香油が……ああ、あった。残ってて良かったよ、昨日の火で燃えたかと思ったが」 きん、と投げ捨てられた硝子の蓋が澄んだ音を立て、どこか暗がりへと転がり消えた。 青年は掌へと中身を垂らす。途端むせ返るような薔薇の香りが鼻腔を刺し、ロイは僅かに息を止めた。 「………凄い香りだ」 「このくらいじゃないと、血臭が消えないんだよ。人間ならいいんだが、犬なんかはね……いちいち吠えられるのもうるさいから」 再び伸し掛かりながらふと嗤い、薄く口付けて青年は囁いた。 「でも、アンタもこの匂いが移るんだぜ。あんまり好きじゃないようだけど、慣れておけよ」 「………嫌いなわけじゃない、さ。ただ、………酔いそう、な、だけ……で、」 言葉半ばにぬめる指を呑み込ませると、唇が、伏せた瞼が震えた。青年はその瞼へと口付けた。突いた掌の下で、棺の蓋が軋む。 「…………っ、」 指を増やし、ぬめりのままに押し込むと痛んだのか呼吸が詰まる。 なんとか呼吸を整えようと開く唇に、小さなままの牙でくすぐるように歯を立てる。そうしながら口腔に舌を差し込めば震える血の塊に触れ、その熱にエドワードは薄く笑んだ。 「………ッう……」 入り口を小刻みに犯しながら三指目を加え、ぬめついた音を立てていた香油が溶けて水音に変わるのを愉しんでいると、きつく折り立てさせた膝が焦れたように揺れた。 「なに……もっと奥まで触って欲しい? でもここ拡げておかないと、また傷が開くよ」 抗議するように睨む眼を無視して卑猥な調子で囁き、エドワードは第一関節までを呑ませた指をゆっくりと捻る。 「……あんまり負担掛けて寝込まれでもしたら、アルが心配するからな」 何か言いたげに開き掛けたロイの唇に立てた人差し指を当て、青年はしい、と沈黙を要求した。 「アンタの口からアルのことは聞きたくない。……殺してしまいそうだから」 怪訝そうな黒い眼に酷薄に笑み、エドワードは触れるか触れないかの加減で頬を辿り、首筋に触れた。 「何故アンタを連れて行くことにしたと思う? アルは、アンタほど他人に懐いたことはないんだよ。手紙でもアンタのことばかり書いて来て、オレが帰ってからもずっと神父さまがどうしたこうした、」 噛み跡に触れると微かに身体が強張った。それに構わずエドワードはこねるように傷に触れ、僅かに爪を立てる。 「………オレは嫉妬深いんだ。アンタ個人には興味があるがね、アンタがアルに愛されているかと思うと……食い殺したくなる」 実際、殺すか生かすかは気分次第だったんだ、と薄く嗤ってエドワードは指を奥へと押し込んだ。香油に滑り抵抗無く指の付け根まで呑みはするが苦痛を感じるのか、ロイは僅かに顔を歪めた。 短く、呼気が洩れる。 「………私はあの子を愛しく思っているよ」 「聞きたくないと言っただろう」 「あの子が……愛しく思う、君のこと……も、」 ぎらりと剣呑に輝いた金の眼が、続く言葉にふと緩む。 「愛しく思えれば───いい、と、そう」 真意を窺うように無言でいるエドワードの頬を手で包み引き寄せて、ロイは薄く開いた瞳で笑みをかたどった。 「お前は哀れだ。……哀れで、浅ましく、どうしようもなく……汚れているが、そのお前を愛しく思うことを、神はうとみはしないだろう」 「……その哀れなオレに慈悲を掛けてくれるわけか」 「そうだ。……嫌かね? まともに愛して欲しいなどと……そんな青臭いことを言う気か?」 軽口の体で囁かれた言葉に、エドワードはく、と笑うと笑みを浮かべたままの唇へ音を立てて口付けた。蠢かせていた指を引き抜く。 掌に残る香油を取り出した欲になすり、最奥へと押し当てると瞼を閉ざしたロイが脱力するように小さく息を吐いた。左腕はエドワードの襟首へとすがり、右手が袖口を緩く掴んでいる。 「…………ッ、」 掴まれたシャツに皺が寄った。顎を逸らし喘ぐ様を細めた眼で見下ろしながら、エドワードは殊更ゆっくりと欲を押し込んでいく。 「う………っく、」 熱のない、冷ややかな肉が体内へと侵入してくるその感触に慣れないのか、強く瞼を閉じてじっと嫌悪を堪えているかのような顔を見つめながらエドワードは全てを押し込み軽く腰を揺らした。突いた裸足に力が籠もり、棺が鈍く鳴く。 身を屈めて薄く口付け、エドワードはふいに片腕をロイの背の下へと滑らせ、身体を密着させた。 「────ッア!」 僅かに浮いた腰に驚いたのか短く声を上げ、咄嗟に両腕が青年の背に回る。互いの胸の合間にあるロザリオが灼けた音を立てるのに、びくんと竦んで慌てて腕を緩めるのを赦さずエドワードは密着した腰を強く揺すぶった。 耳許で震える喘ぎが微かに響く。すがり付くようにシャツを掴む背の熱い掌に微笑し、エドワードは黒髪の被る耳翼に舌先を這わせた。 「こ、の……馬鹿……ッ、ロ、ザリオ、が」 最奥を貪られる衝撃にすがる腕を解けないまま、ロイが切れ切れに毒突いた。 「いいよ、気にしなくて……こんな火傷、直ぐに消える」 「痛み、も……ない、の、か……?」 「痛いよ」 「………ッ、なら、」 「こんなもん、飢餓の痛みに比べたら、全然。………飢えはアンタが満たしてくれんだろ? 安いもんだ」 「自虐が趣味、か……?」 悪趣味だ、と呟いて、震える指を引き密着する膚の合間に滑らせ神父はロザリオを握り、抜き取った。滑り落ちた銀の十字はかつん、と棺を叩き、揺れる。 ロイは甘やかな息を吐き、再び青年の背に腕を回した。エドワードは微かに苦笑を浮かべ、最奥を突きながら左脚を撫で下げ、踝の目立つ足先をやんわりと掴んだ。そのままゆっくりと持ち上げ肩へと担ぎ上げ、腰を捻らせる。 「は、………ッ」 しがみつく指が時折脱力する。背がしなるたびに銀鎖が擦れて、硬質な音を立てた。 「なあ……気持ちいいんだろ? ……もういきそう?」 覗き込んだ黒い瞳は眇められ、目元に朱を乗せる。切れ切れに吐く息は発熱のせいばかりではなく熱く、噛み付くように口付ければ差し入れた冷たい肉を求めるように、酷く熱い舌が絡む。 「…ァ………ッ」 掠れた声を上げ一際強く背をしならせ、ロイは腰を強く押し付けた。その要求に満足げに笑み、エドワードは腰を抱え直し更に膚を密着させて強く律動する。 「………薔薇の香りは媚薬なんだよ、神父さん」 半ば抱え上げるようにして、すがり付く耳許に囁きを吹き込む。 「これから……アンタに染み付く香りだ」 慣れておけよ、と笑みを込めて囁いて、エドワードは一際強くえぐった。生きた身体の体温を移して温まっていた膚に、熱い飛沫を感じる。 遂情の波に逆らわず、青年はロイの体内へと欲を放った。 体内に注がれる低温に身体を震わせて、ロイは小さく安堵のような喘ぎを洩らした。 |
8<< >>10
■2005/8/2 棺桶の中のひと大迷惑。
■JUNKTOP