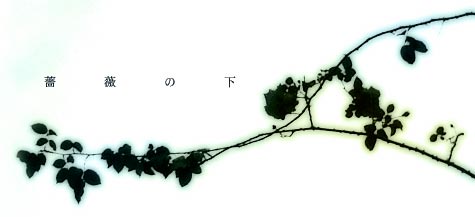
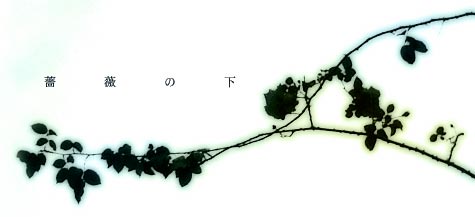
| 「遅かったな、神父さん。陽があるうちに来るかと思ったよ」 燭台を手にゆっくりと歩み寄ったロイに、不作法に棺の上へと腰掛けていた青年は組んだ足の上に広げた書物から視線も上げずに本借りてるよ、と軽い調子で言った。 「………こんな闇の中で文字が読めるのか」 「まあな」 上目遣いに金眼を向け、にやりと笑んでエドワードは書物を閉じ傍らに積まれていた数冊の上へと乗せる。表題の、Bibleと押された金文字が、一瞬炎を反射してきらりと輝いた。 「それで? 白木の杭でも持って来たか?」 そうからかってみるが、神父は答えず少し離れた棺へと燭台を置き、緩慢に身を向けてゆっくりと歩を進めた。暗い炎の灯りの元で尚その顔は蒼醒めている。 「………血が足りないか?」 「あれだけ貪っておいてよく言う……」 「食事も取っていないんだろう。回復しないぜ、それじゃ」 「アルフォンスに話を聞いた」 わざとらしく気遣う顔を見せたエドワードに取り合わず、神父は数歩離れて立ち止まり、じっと青年を見下ろした。 「………あの子は何者だ。人間なんだろう」 青年は肩を竦め掛け、それからふっと表情を落として神父を見つめた。 「いいや、オレと同種だよ」 「嘘を吐くな。あの子の身体は温かいし、何より太陽の光を浴びてもどうもしない。大体、あの子が生き血を貪り吸わねばならない存在なのだとしたら、こんな小さな街に二年も居れるはずがない」 「アンタ肝心なことをひとつ見落としてるよ、神父さん。……街の他の連中……特に女どもの中には、もう疑問に思ってる奴もいるようなのに」 眉を顰めたロイに、エドワードはゆっくりと噛み含めるように囁いた。 「思い出してみろよ。……あいつは、出会った頃と比べて背は伸びたか? 体重は増えたようか? 声は低くなったかい?」 「…………、」 「あの年頃の子供が二年もの間、全く変わらないとそのことを……アンタ、不思議だと思ったことはないか?」 ふいに唇を歪めて笑みを取り戻し、青年は手を差し伸べる。神父はその手を見つめ、意外にも素直に応じるようにゆっくりと一歩を踏み出した。 「目醒めが遅いだけさ。……目醒めるまでは、オレたちは人間に擬態するんだ。生まれて間もないうちは吸血鬼と言えどもまだまだ力弱い存在だからな、人間が束になって襲い掛かってくれば、簡単に狩られてしまう」 「…………」 「………だが、そろそろ目醒めてもいい頃だ」 指を取り腰を抱き寄せ神父を見上げ、青年は酷薄に笑む。 「だから連れて行くんだ。───血の匂いを纏うオレと共に在れば、すぐにでも闇の血に目醒めるだろうな。無限の力と永遠の命と夜闇のかぐわしさに気付くのも、あと少しだ」 爪の長い指でゆっくりと僧服の合わせを開きながら、青年は囁く。神父は青年の腕に手を置いたままじっとその様を見下ろしている。 「それを、阻止したくはないか、神父さん?」 「…………。……だから私を連れて行く、と?」 「いいや、そそのかしているだけだ。アンタが居ようと居まいと、アルフォンスをこちら側へ導く自信がオレにはある。……だが、目醒めるまでの間、昼の間あいつの面倒を見てやれる者が必要だ」 「私がアルフォンスへとお前の正体を明かして、連れて逃げるとは考えないのか?」 「無理だね。アルの気配なら世界中のどこにいたってオレには解るし、大体、オレの正体が引き金となってあいつが目醒めてしまうかもしれないとなれば、アンタはそれをあいつに告げることは出来ない」 合わせに手を差し入れ、肩から黒衣を滑らす。とさ、と乾いた音を立てて冷たい石の床へと僧服が落ちた。真白なシャツの上、ロザリオが光を集めて薄く輝く。 「………抵抗しないな。何を考えている?」 無言のロイに軽く肩を竦め、青年はふいに強くその腕を引いた。倒れ掛かる身体を抱き留めて、棺の上へと押し倒す。ロイが酷く不満げに眉を顰めた。 「冒涜だ、」 「何、死体の上だから?」 死人には何も出来ない、と嗤う青年にロイは呆れたように溜息を吐いた。 「お前こそ死人の癖に」 「なかなか倒錯的でいいだろう?」 言いながらも青年の指はゆっくりと、けれど止まることなくシャツのボタンを外し皺の寄った眉間へと冷たい唇を落とした。 「…………、……何だ」 身を寄せた青年の髪を、ゆっくりと持ち上がった腕がまるで慈しむように撫でた。エドワードは訝しげに漆黒の眼を覗く。 神父は、酷く慈愛に満ちた表情で穏やかに微笑んだ。 「可哀想に、お前」 「────、」 「私を連れて行きたいのは、生き餌がなければ食事に出るたびアルフォンスが疑問に思ってしまうからだろう?」 「……何を、」 「陽の匂いのするあの子を愛しているのだろう? 夜闇の───血の臭いを薔薇の香りで誤魔化さねば人間と付き合うことも出来ないようなそんな浅ましい存在に、あの子を堕としてしまいたくはないのだろう」 可哀想に、ともう一度囁いて、熱を持つ熱い掌が青年の頬を包み引き寄せた。額を触れ合わせ、祈るように閉じた瞼が、蒼い。 「───私を汚し堕落させてしまいたいのも、不要な傷を負って帰ってアルフォンスに疑われたくないからだ。あの子を置いて長く姿をくらますのもあの子を人間の世界へおいておきたいからだし、それでも会いに来てしまうのは───変わらないあの子が迫害を受けていないかと心配で、何より……会いたくて堪らなくなるからだろう」 「………馬鹿な、」 反駁し掛けた唇を、神父の指が覆った。 「お前が、真摯に愛を認め懺悔をすることの出来ない存在であることは解っている」 青年はじっと、瞬きもなく金の眼を神父に据えた。ロイは笑みのように、薄く眼を細める。 「………お前たち兄弟と、共に行こう」 呆然と見つめる金の眼にふいに悪戯を企む子供のような笑んだ視線を向け、ロイは僅かに顔を逸らしてエドワードを斜めに見上げた。首筋に穿たれた小さな穴が露わになる。 その、まるで誘う女のような仕草に青年は大きく瞬いた。 「言っただろう? ───神の愛を知れば、地獄ですら神の御許だと」 陶然と神父は続ける。 「信仰は教会にのみあるものではない。信仰は……神は、常に我らと共に在る」 「───それがアンタの哲理か」 「いいや。この命の全てだよ、エドワード」 |
7<< >>9
■2005/8/1 どうもカトリックとプロテスタントの考え方を混同したようです……(いやネットでさらっと調べただけなのでアレですが)この神父さん、凄い異端だと思われる。
……か、架空の宗教ということでお願いします……(目逸らし)
■JUNKTOP