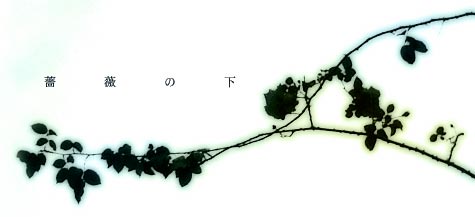
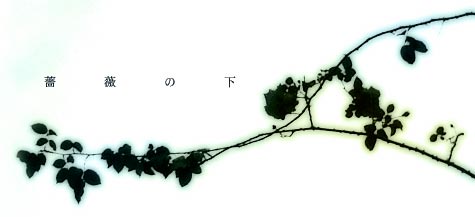
| 神父さま、と気遣わしげに囁いた声に、ロイは一度閉じた瞼を再び持ち上げた。 「神父さま、……気分はどうですか?」 不安げな面持ちで覗き込む少年に、ロイはふと安堵のように頬を崩しそろそろと指を伸ばしてそのすべらかな、健康的に薔薇色に血の色を透かす頬を包む。 温かい。 ああやっぱりこの子は人間じゃないか、と胸の裡で呟きふっと重くなった瞼を落とすと、同時に滑り落ちた手を握られた。 小さな掌が血の気の失せた、冷ややかな指を温かく包み体温を分ける。 「手が凄く冷たい……なにか、温かいものを食べたほうがいいです。せめてスープでも」 「………いや、」 絞るように喉を震わせれば、意外にもしっかりとした声が出た。ロイはひとつ息を吐いて眼を開く。 「食事はいい。……後でもらうよ、アルフォンス」 でも、とまだ口籠もりながら、それでもロイの意識がはっきりとしていることに安堵したのかアルフォンスは強張っていた頬を緩めた。ロイは周囲を見回す。見慣れた自室の寝台の上だ。 「………どうしてここに?」 「あ、ええと……今朝になっても兄さんが帰って来なかったから、ご迷惑になってるかなって様子を見に来て、そうしたら神父さまが具合を悪くされてしまったから帰るに帰れなかったって言われて、ボク、吃驚して……やっぱり昨日から身体の調子良くなかったんですよね、すみません夕食に誘ったりして」 頭を下げる少年の金髪をくしゃりと撫でて宥め、ロイはきちんとカフスの留まった袖口を見、それから己の口元をそろそろと撫でた。薄く髭は浮いてはいるが、腐った血に汚されたはずの膚は生臭い残滓などひとつもなく、行水でもしたかのように綺麗に拭い取られている。それは他の部分も同様で、鈍く痛みはしたが不快な感触はない。 「………兄はどうした?」 「あ、まだ陽が落ちないので……地下にいます。ごめんなさい、勝手に……」 「いや、それは構わないが……地下墓所に?」 「ええ。兄さん、そういうの全然怖くないひとだから」 小さく肩を竦めるアルフォンスに苦笑めいた笑みを向け、ロイは半身を起こした。慌てたように差し出されたアルフォンスの手を借り、僅かに襲った目眩をやり過ごす。明らかに血が足りていない。 「大丈夫ですか? 熱が下がったばかりなのに……」 「………熱?」 ええ、と不安げに眉を曇らせてアルフォンスは頷いた。 「熱が高かったんですよ。薬は服ませたからって兄さんは言ってたけど、ボク心配で、夜までに下がらなかったらお医者さま呼ぼうって思ってたんですけど」 「いや、それには及ばない」 僅かに慌てて申し出を断り、ロイはきっちりとボタンの留められたシャツの襟を押さえた。僅かに痛んだ首筋が、あれが夢ではないことをはっきりと告げている。 そうですか、とまだ不安げに頷いて、アルフォンスはそれ以上は言わずにふと視線を落としもじもじと手指を遊ばせた。 「アルフォンス?」 どうした、と尋ねると、少年はあの、と呟き視線を落としたままぼそぼそと口を開く。 「兄さんが……、来週には、発つって言ってるんですけど」 「………ああ、」 それが本当なら僥倖だ、と内心で頷きながら、ロイは素早く思考を巡らせた。 あの悪魔が去ったなら、まずアルフォンスをどこか、あれに見つからない土地へと移り住ませねばならないだろう。自分が付いて行くのが一番だが、再び戻ったあれが弟の不在に気付いたときにこの街の住人にどんな報復をするともしれない。それを考えれば、画策をする自分が矢面に立つ必要はありそうだ。 この小さな少年の成長を見守ってやれないことは、気掛かりではあるのだか。 しかしそんな保護者然としたことを考えていたロイの思考を遮るように、もじもじと俯いたままのアルフォンスは言葉を重ねた。 「あの、……ボクも一緒に行くことになってて」 はっと向けたられた視線の鋭さに驚いたのか、アルフォンスは慌てたように両手をぱたぱたと振った。 「あの、いつもそうなんです。この街はちょっと長くいたけど、いつもは二年も経たないうちに兄さんが迎えに来て、また別の土地に引っ越して、そうやってずっと来たんです。だから多分今回もそうなんだとは思ってたんですけど、……いつもより急ではあったから、ボクも吃驚はしたんですけど………」 アルフォンスは上目遣いに何か探るようにロイを見つめた。 「あの……神父さま」 「……なにかね」 「兄さんが……、これからは神父さまが一緒に来てくれるから、寂しくないよって、」 ロイは大きく瞬いた。その隠せなかった驚愕に慌て、アルフォンスは再びぱたぱたと手を振る。 「あっ、そうですよね、神父さまは教会守って行かなきゃないんだし……兄さんって強引なとこがあるから、もしかしたら神父さまからちゃんと承諾もらってないかもってそう思って」 ごめんなさい忘れてください、と頭を下げる少年のつむじを見下ろし、ロイは混乱のまま幾度か瞬いた。窓から差し込む夕焼けは次第に青く明度を落とし、音もなく夜が歩み寄る。 「………アルフォンス」 「は、はい」 ロイは微笑み、少年の金髪を撫でた。 「暗くなる前に帰りなさい。なに、今夜は兄さんはちゃんと帰らせるから」 「………でも、」 「少し彼と話がしたい。……何しろ、初耳の話なものでね」 それとも送って行こうか、と寝台から降り掛けるロイをアルフォンスは慌てて留めた。 「あの、一人で大丈夫です! 神父さまはもう少し安静にしててください。顔色凄く悪いし」 「大丈夫、少し貧血気味なだけだ」 「駄目です、本当に熱が高かったんだから! 大人のひとって自分の体力過信し過ぎですよ。台所にスープを作ってありますから、落ち着いたら食べてください。あと今日は早く休んで、兄さんの長話なんかに付き合わなくていいですから、追い返してくださいね。明日の朝にボクまた来ますから、具合悪かったら無理に起きなくても……」 「ああ、解ったよ、アルフォンス。有難う、忠告は有難く拝聴した」 くつくつと笑い金髪を引き寄せ太陽に香の匂うつむじに口付けて、ロイは少年の頬を撫でた。 「では、また明日な、アルフォンス」 「………はい、神父さま」 にっこりと微笑んで、少年は行儀良くぺこりと頭を下げた。 |
6<< >>8
■2005/7/31 神父さんは素直なアルフォンスくんが可愛くて仕方がない。……びみょーにペドくさいですけど親愛(つか、アガペー)ですよ(一応)。
■JUNKTOP