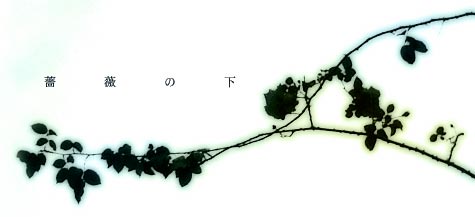
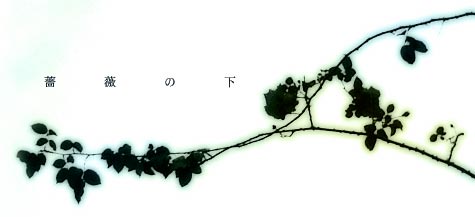
| 「エドワー……、」 「───神父さん、アンタ」 掠れた声が、燃え盛る炎越しに切れ切れに届く。ばさ、ばさと音を立てて、青年の足下に煤が落ちる。衣服か髪か、でなければ皮膚か。 ふいに、青年が──笑んだ。 炎の中にくっきりと白い牙を覗かせ、瞠った眼が弓形に歪む。 く、く、と、僅かに洩れるそれが笑みだと気付きロイが身動ぐのを待っていたかのように、炎に包まれていた腕が伸びた。 炎に巻かれ真っ黒だった手は僧服に包まれた腕を掴む前に火を払い、今の今まで燃え盛っていたのが嘘のように真白で冷ややかなそれが肉に食い込む程に力を込める。 「アンタ、今日は何を食べた……?」 くつくつと喉を鳴らしながら、濡れた髪を掻き上げでもするかのような気安い仕草で青年は一つ頭を振る。それだけで空気を灼いていた炎は布地がはためくような音を立てて消えた。 「やれやれ、外套と上着を駄目にしたよ。どうしてくれるんだ神父さん、アルが選んでくれたのなんだぜ、……気に入ってたのに」 「何……の、ことだ」 「うん? だからアルが、」 「食べ物だ。何が、」 微かに震える声に気付いたのか、青年はうっすらと微笑みふいに掴んだ腕を引いた。ロイは堅い石の床へと膝を突く。手を離れた燭台が滑り、倒れた蝋を焼いて燃える。 「昨夜俗の酒を飲んで、男の精を受けて───その神から遠離った身体になにをしてやったのか、って訊いてるんだよ」 ゆっくりと伸し掛かりながら答えが解っているかのような問いを囁き、青年は嫌な笑みを浮かべた。 「離……せ、悪魔などにくれてやる血も肉も持ち合わせては……」 「アルがパン持って来たろ? アンタ、それを食ってやったろう? アルのことだから、まめまめしくアンタの世話を焼いたよな? 茶を淹れて、残り物を調理し直したりしてさ。……カミサマから授かったパンと葡萄酒ではなしに、俗人の焼いたパンを、俗人の淹れた茶で片付けたろう?」 夜もアルの飯を食ったよな、と青年は可笑しそうに囁く。 「今朝はちゃんと眼が醒めたか? 朝のお祈りはサボらず捧げたか? カミサマに懺悔は済んだのかい。……神職者ってのは聖別されてるものだがな、それは信仰の賜だ。聖別されていない今日のアンタに、オレを焼き尽くすだけの力はないよ。───たとえ神の火だとしてもだ」 ロイは凝視していた視線に力を込めた。 「───貴様、アルフォンスを利用したのか!? 弟を………いや、あんな子供を、何のために……!」 「おいおい、何勝手に勘違いしてんだ? パンを持って行ってやれと言ったのも夕食に誘えと言ったのもオレだが、でも別に、アルを騙してるわけじゃないんだぜ。オレはアイツを愛してるからな」 可愛い弟だ、と囁いた顔は変わらずどこか揶揄るような、皮肉な笑みが浮いている。 「ふざけるな、あの子は人間だ! 陽の光の似合う普通の少年だ! 貴様のような体温の無い悪魔と兄弟のわけが」 「ああ、確かに今のアルは人間に近いな。………だが、確かにオレと血を分けた兄弟だ」 嘘だ、と狼狽えた掠れ声でロイは囁く。 「………信じない」 「ああ、まあ、神父さんに悪魔の甘言を信じろとは言わないさ」 それでも現実はここにあるものなんだぜ、と睦言の甘さで囁いて、エドワードは小さくなった牙でかり、と鎖骨を食んだ。針で引っ掻くような痛みにロイは眉を寄せる。首に絡んだロザリオの鎖がしゃり、と場違いに涼やかな音を立てた。 「………止せ、」 「なんだ、お願いか? お願いなら代価を要求するが」 「命令だ。貴様が悪魔であるのならここにいるべきではない。ここは神の住まう場だ」 エドワードはゆっくりと赤い舌で唇に付いた血を舐め取る。 「それを汚したのはアンタだよ、神父さん。鍵を開けて、ご丁寧に『入れ』とオレを招き入れたじゃないか」 ロイは眼を瞠る。エドワードはくつくつと喉を鳴らした。 「オレは制約の多い悪魔なんだよ、神父さん。家人が鍵を開け招き入れてくれなければ、他人の家へ入ることは出来ない」 瞠った双眸が悔しげに歪む様を嘲るような笑みを浮かべたまま眺め、エドワードは満足げに金眼を細めた。 「アンタ、警戒していただろう? オレを、よりにもよって聖堂なんかに招き入れたくはなかったはずだ。……だが、アンタは予感を信じなかった。無意識に、そんなものは迷信だと片付けた。アンタの中に居座る科学者の血がそうさせた」 く、く、と楽しげに嗤い、エドワードは易々とロイの両腕を纏めて黒髪の上で押さえ込み、自由になった右手でゆっくりと僧服とシャツの合わせを撫で開く。 「アンタはアンタとアンタの神を信じるべきだったよ、……マスタング神父」 「私が神を信じていないとでも……!」 「いいや? だが、神の奇跡を信じてはいないだろ。奇跡を無闇に信じ込むことは堕落に繋がる、そうだろう?」 傷をなぞるように這う指の冷たさに、ロイは逃れようと身を捩る。 「離せ……!」 「いいだろ、別に。減るものでもないし、どうせ初めてじゃないだろう、もう」 今更、と嘲るように嗤う青年をロイは睨み付けた。無理に頭上へ纏め上げられている腕が、肩が軋む。 「何が、目的だ……」 「目的? ……別に、何も? 清らかな神父様を堕落させてみたいだけだよ」 「───ほう、そうか」 戯れの色の強い言葉に、ふいにロイは強く笑んだ。その勝ち誇ったような笑みにエドワードは不審げに瞬き、組み敷いた身体から抵抗の力が抜けたことに眉を寄せた。 「なんだ?」 「やってみろ」 「ああ?」 ロイは唇の片端を歪め粗野にも思える下卑た笑みを青年へと向けた。 「私は堕落しない。悪魔たる貴様になど理解は出来んだろうが、神は罪人を哀れむ。善も悪も、神の子である我々を、皆平等に愛し哀れむものだ。神の愛は底が知れない」 見くびるな、と酷く優しく囁いて、ロイはうっそりと笑った。 「───神の愛を知れば、地獄ですら神の御許だ」 「……………」 エドワードから表情が失せた。 白い仮面のような顔に金の眼だけを光らせて、青年は無言のままゆっくりと唇を舌で舐める。ちらりと覗いた牙を伝い、獲物を前にした獣のようにつ、と唾液が一筋落ちた。 一言も言葉を返さず鋭く牙を剥き、青年は神父の首筋へと唇を埋めた。 |
3<< >>5
■2005/7/29 吸血鬼/ヴァンパイア/Vampire
不老不死/夜行性/明かりが一切無くてももの見える/家人が内側から招き入れなければ初訪問の家へは入れない/流れる川を渡れない/鏡に映らない/太陽の光で灰になる/白木の杭で心臓を貫かれると灰になる/大蒜苦手/聖水とか聖印とか聖別されたもの苦手/銀苦手/休息や復活に邪悪な土が必要/狼や蝙蝠や鼠などを僕として召還・使役可能/狼や蝙蝠や鼠などに変身可能/霧に変身可能/空飛べる/超怪力/回復力異常/視力聴覚嗅覚獣並みっていうか獣以上超いい/ていうか身体能力異常に高い/視線での魅了(もしくはフィア)が可能というか基本/心読んだりすることもある/魅了した者を操ったりすることもある/冒頭の神父は操られてふらふらひとりで帰って来たために記憶が曖昧なのだと思われる/だってエドワードさんその時点では教会は入れないもんベッドまで運べない/灰になっても邪悪な土があれば復活する/けど、灰を川に流せば復活できないとか言われたりもする/多分流してもえどわど氏は邪悪な土があれば復活するいろいろ混じってますがとりあえずヴァンパイアは制約が多い。漫画小説の類いだと血の他は赤ワインと薔薇の花弁の浮いた紅茶ばかり飲んでる印象もなくはない。耽美? でも首を落としても焼き尽くしても復活しちゃう凄い面倒臭い耽美というより退廃主義というかグロというかな化け物。アンホーリー・ソイルを全部処分されちゃうと復活できなくなるので退治の際は予め処分しておくのが望ましいですが全国各地津々浦々の吸血鬼えどわど氏の土の在り処を全部把握するのは難しいかもしれない。あと追い詰めてもばらっと大量の鼠や蝙蝠に化けて逃げてしまったり霧になって逃げてしまったりするので捕獲も大変。頑張れ神父。(そういう話じゃないです)
■JUNKTOP