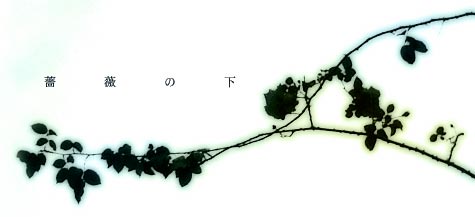
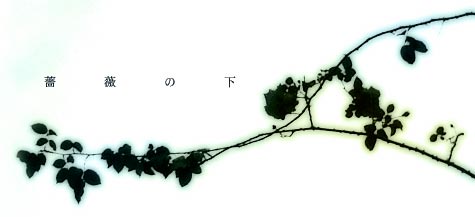
| ぎり、と食い締めた歯が軋む。 「───ああ、傷が開いた」 愉しそうに囁いて、青年は血液にぬめる二本の指を蠢かす。思わず、と言ったように白い喉を仰け反らせ、ロイは微かに呻いた。その額へ浮かぶ汗は冷たく、膚からは血の気が引いている。 「昨夜はアンタあんまり暴れるから、つい乱暴にしちゃったんだよな」 うっすらと開いた黒い瞳は硬質な理性の光を乗せていて、その様にエドワードは嬉しそうに微笑んだ。 「でも最後の方は、アンタも気持ちよかったみたいだぜ。生き物は快楽に弱いものだ……そうだろ? だが神はそれに溺れることを赦してはいない、……違うか?」 ゆっくりと慎重に、呻きを混ぜないよう細く震える吐息が洩れた。 「………しつこいぞ、悪魔め……」 「へえ、しつこくされるのは嫌? じゃあいつまででもなぶっていてやろうか」 アンタが嫌がるなら、とわざと意味を取り違えてまだ血の流れている首筋に穿たれた傷口を舐め、青年は殊更ゆっくりと内部を押し開く。 指を引き抜き、体液混じりの血に濡れたそれを見せつけるように舐めると青年の狙い通りに神父は顔を歪めた。 その酷く嫌そうな表情に満足し、エドワードは腿へと掌を滑らせる。絡む下衣を更にずらし、左脚を担ぎ上げると僅かながらに抵抗があった。 肩を蹴る足を簡単にいなしてエドワードは膝を押し遣り組み敷いた身体を強引に折り曲げる。 「糞……ッ、獣めが」 「獣の体位が好きなら次はそうしてやるよ」 今更の罵りににやにやと笑んだまま囁き屹立した欲を傷付いた最奥へと触れ、二、三度擦り付けるように先端で撫でる。 揺れた黒い眼が何かを探し青年を越え、その背後に立つ磔の御子を捉えたのに気付き、ふいに湧き上がった赤い感情のままエドワードはその身体を押し開いた。 「────ッぐ、う……っ!」 呼吸を貪るように大きく開かれた唇から悲鳴が洩れる前にぐっと噛み締め、きつく瞳を歪めてロイは呻く。視線はまだ十字架へと据えられたままで、その被支配の仕草が青年の嗜虐心を煽る。 「………おい、今アンタに突っ込んでんのはカミサマじゃなくてオレなんだぜ。そんなに熱烈な視線を送ったところで、カミサマはアンタを顧みちゃくれない」 答える言葉はなく、ただ時折押し殺した呻きが洩れるだけだ。より大きく傷が開いたのか生温かい濡れた感触が下肢を濡らす。 「う……ッ、」 露わになった胸が大きく上下し、その筋肉の上でロザリオが滑りきん、と硬質の音を立ててロイの口元へと落ちた。ロイは音の在処を探ろうと視線をさまよわせる。エドワードは無表情にそれを見下ろし、強く腰を押し付けて強引に結合を深くした。 青年は震える唇に己のそれを深く重ねた。冷たい舌で失血に熱の落ちる、けれど青年のそれよりも遙かに熱い口内を探る。 「────ッ!」 呼吸もままならず苦しげに眇められていた黒い眼がぎらりと光った、と思った刹那、強い痛みが走った。 噛まれた、と気付き舌打ちも出来ずにエドワードは冷たい舌を噛み切る勢いで力を込める顎に指を掛け、こちらも力任せにこじ開けた。青年の無慈悲な指が顎を砕く前に噛み締める力を弱めたロイは、半ば以上噛み切った舌を口内から追い出して溢れる生臭い血にむせる。 有り得ない勢いで血を落とす半ば以上千切れた赤い肉塊を口内に納め唇を閉じ、青年は神父の唇に再び指を掛けて横向かせむせ返るままに血を吐かせた。 「全部吐けよ、飲むんじゃない………神の世と引き替えに、不死を得たいと言うなら止めないが」 言って、唇と顎を汚す色鮮やかな血を舐めた舌にはもう傷は微塵も見られなかった。 色ばかりが鮮血じみて赤い、生臭い腐ったような臭いを放つ死んだ血にむせ返りながら、ロイは涙に濡れた眼でそれを見上げて何か毒突いたようだった。エドワードは薄く嗤う。 「馬鹿だな、神父さん。こんなことじゃオレは死なない」 やたらと優しい仕草で喘ぐロイの口元に残る血をその冷ややかな掌で拭い、口内へと親指を差し込んでこじ開けエドワードは唇を寄せた。 「噛むなよ、」 言って、ゆっくりと体温がないままの舌を差し込み口内に残る血を舐め取る。 頬に右手を添え、僧服を纏わせたままの腕を拘束していた左手を解放する。ぱたり、と投げ出された腕は暫くはそのまま放られていたが、やがてずるずると引き下ろされ首もとを探り、左手がロザリオを握った。 唇を離すと震える息を貪り喉を鳴らしたロイが、恐る恐る、というように瞼を上げた。投げ出されていた右手が緩慢に持ち上がり、己の上へと降る金髪を緩く指に絡めてエドワードの襟を力無く掴む。 と思えば、半ばまで開かれていたシャツの合間から左手に握られたロザリオが押し付けられ、陶器のように白い胸が焼けた鉄に水を落としたかのような音を立てて焦げ付いた。エドワードは子供をあやすかのような曇りのない微笑を浮かべて押し付けられた手はそのままに、汗に湿る黒髪を撫でた。 「まだ解んないのか、神父さん。……今のアンタは神から遠いよ。そのアンタが、そんなものを使ったところでオレは退散しないぜ?」 酷く優しく目元へと口付ける青年に、ロイはじっと身動ぎせずにいる。細い息はまるで瀕死の獣のように短く早い。 「……………」 やがて諦めたのか左手が下ろされた。まだロザリオを握ったままのそれをそっと掌で包み撫で、青年は神父の胸の上へと下ろす。聖印へと触れた指が音を立てて焦げたが、それに構わずに乱れた黒髪を梳けば戸惑ったような瞳と視線が合った。 「お前………本当に、何が目的、だ……?」 「うん? 堕落させたいってことじゃ駄目なのか? それならそうだな、」 エドワードはくつくつと笑い薄い瞼へと口付けた。 「………アンタを手に入れたいと、そう思った……これならどうだ?」 「馬鹿を……」 「もういいだろ、余計なお喋りは。なかなか愉しかったけどな……そろそろよくなろうぜ」 「……ふざけたこと、を……」 「力抜けよ」 傷を擦られる痛みにみるみる冷や汗を浮かばせる額に唇を落とし、エドワードはゆっくりと擦り上げた。 「声出せよ。……カミサマに見せつけてやれよ、アンタの全部を」 「…………ッ、」 「堪えるな。赦してもらうんだろう? ───罪人なら罪人らしく、全て晒して赦しを請えよ」 噛み締めた唇が傷付きそうで、エドワードは舌先で震えるそれをゆっくりと舐めた。肩に掛かる指が、脱力するのか幾度も滑ってはそのたびすがるように握り直す。 「………気持ちいいだろ? どれだけでもなぶってやるよ、アンタが満足するまで」 「ん……ッ、」 「大丈夫、アルには言わないよ……こんなことは。誰にも───何にも、アンタの大事なカミサマにもね……」 左手は血の気が失せるほど強くロザリオを握るが僅かに開いた瞼の奥の夜闇にはもう意識の色は無くて、エドワードは微かに苦笑した。 「───貪り過ぎたかな、」 呟き、切れ切れに喘ぐ唇に口付ける。 触れる息は熱く、どれだけ昂ぶっても熱くなることのない青年の氷の息と混じり合い、互いの口内へと呑まれた。 |
4<< >>6
■2005/7/30
■JUNKTOP