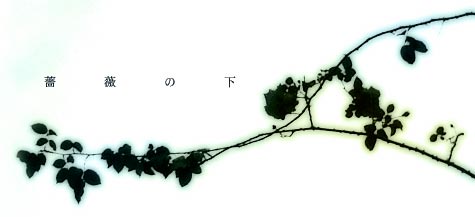
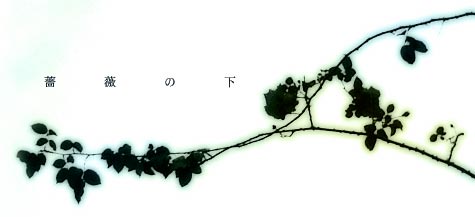
| 結局真意を問い質す前にアルフォンスが戻り、うやむやのままに話は終わってしまった。どうも、このエドワードという男は相手を翻弄する物言いをする人物のようだった。 しかしアルフォンスへ向ける慈しむ視線や若者然とした物言いはどこから見てもただの弟思いの兄で、やはり嫌われたかな、と考えながらも結局深夜になってから暇を告げたロイは、送って行くと言い出したエドワードを断り切れずに今こうして、男二人で夜道を連れ立っている。 「───この街は、どうだい」 一歩後ろから響いた声に、ロイは振り向かずに問い返した。 「どう、とは?」 「ひとの気性さ。田舎町は当たり外れが激しいからな。余所者に冷たい連中ばかりの中にアルフォンスを置いて行ったとなれば心が痛む」 「ああ………」 ロイは薄く笑った。 「どこの街でもそうだが色んな人間がいはするからね……、だが、悪くはないと思うよ。少なくともアルフォンスを気に掛けて面倒を見てやっていた者は一人や二人ではないし、みな概ねあの子には好意的だな。男どもは君にも好意的だよ」 「へえ?」 「仕事で国中を駆け回っている仕事の出来る男、という認識のようだ」 くく、と密やかに笑う声はどこか嘲笑じみていた。 「それは光栄だ」 「今度酒場に連れて行ってやろうか。皆に紹介してやろう」 「まあ……暇があればね」 「なんだ、またすぐに発つのか? アルフォンスが寂しがるだろう」 「いや………、」 僅かに間を置き、その答えを聞く前に背後からすう、と腕が伸び指を差した。 「───着いたよ、神父さん。あの教会だろう?」 話に夢中になっていたつもりもなかったのに見慣れた景色を見逃していたことに慌て、ロイは瞬く。 「あ、ああ……この街には教会はひとつだ」 「そうか。じゃあ、オレはこれで」 「待て、霧で濡れてしまっただろう。少し暖炉で温まって行け。茶を淹れよう」 返事を待たずに僅かに足を早めて先に聖堂の扉へと辿り着き、ロイは来客を連れて勝手口に回る手間を惜しんで鉄の鍵を取り出した。 「入ってくれ、直ぐに客間を暖めよう」 ゆっくりと歩いて来る背後の影に言い置いて一足先に暗い聖堂へと入る。火の気の絶えている祭壇へと足早に進み、ランタンから燭台の蝋燭へと火を移す。 蜜蝋の匂いに知らずほっと息を吐いた瞬間、強い音を立てて扉が閉じた。慌てて振り向く。 「おい、神父さん。開けてくれよ」 ごんごん、と扉を叩く音がする。声の主は苛立った様子もなくのんびりと続けた。 「鍵が掛かってるぞ、開けてくれ」 それともこのまま帰れという意思表示なのか、と笑みを含めた声で揶揄られ、ロイは慌てて扉へと駆け寄る。 「今開ける、少し待て」 扉が閉じた衝撃で落ちたらしい鍵に首を捻りながら、ロイは鍵を上げ扉を開いた。聖堂の薄い炎の灯りに照らされて、金の眼がぎらりと光る。ロイは微かに、そうと知れぬように息を呑んだ。 「………入りなさい」 本音を言えば、このまま───扉を閉じて、しまいたかった。 息が詰まるような胸の苦しさは不快そのもので、ロイは口の中が干上がって行くのを感じながら麻痺しようとする舌を無理矢理動かす。 エドワードの仮面のような白い顔に、酷薄な笑みが浮いた。左右に吊り上げられた唇が言葉を刻む。 「───では、遠慮無く」 ゆっくりと、黒い衣服に包まれた身体が傾ぐように動いた。 丈の長い外套は湿気を吸って重いはずなのに何故か風を孕み、金縛りにでも掛かったかのように視線のひとつも動かすことの出来ずにいたロイの横を擦り抜けた青年の残り香は、むせるような薔薇の香りだった。 「ほら」 客間へと誘えば聖堂でいい、と長椅子へと座り込んでしまった青年はぼんやりと祭壇を見上げていたが、差し出された湯気の立つカップを受け取ると持ち手に手袋を抜いた指を這わせた。 ロイは祭壇に眼を遣る。いつの間にか、一輪の薔薇が燭台の合間に置かれている。 「………これは?」 「ああ、オレが持って来たんだ」 では先程の薔薇の香りはこれなのか、と考えながら何気なく触れた瞬間、ちくりと指先に痛みを感じてロイは反射的に手を引いた。 「指でも刺したか?」 「ああ、いや」 「血の匂いがする」 ロイはふと言葉を納めた。それから冗談を言っているのだと思い至りふと緩み掛けた唇は、笑みを洩らすことなく再び引き結ばれる。 気配など、なかった。 いつの間にかほとんど寄り添うように背後に立った青年の冷ややかな手が、まるで薔薇を取るべきか取らぬべきか迷っているかのように固まっていたロイの手首を掴んだ。 振り払えずにただ硬直しているロイの手をゆっくりと引き上げて、ほとんど抱き締めるかのように近付いた青年は僅かに身を屈め肩口に顎を乗せて、はらりと血の流れた傷口を舐めた。 その、舌の感触までもが酷く───冷たくて。 「────!」 反射的に手を振り払うと青年は容易く拘束を解いた。身を支えるかのように祭壇に片手を突き蒼醒めた顔で振り向いたロイに、青年は薄く笑む。 「そんなに驚くことはないだろ? 消毒しただけだよ」 「……だとしても普通、今日知り合ったばかりの、しかも男の指を舐めはしないだろう」 「そうか? オレはするけどな」 可笑しそうに言ってエドワードはふと祭壇を見上げた。暗い聖堂に伸びる黒々とした十字に、眩しげに金の眼が細められる。 再び伸びた腕に肩を掴まれ眉を顰めたロイを、濡れた外套を纏ったままの青年は笑みを納めぬまま見詰めた。 「離したまえ」 「イヤ」 「同性に迫られる趣味はないんだ」 冗談めかして溜息とともに告げれば、エドワードは笑みを深くしてくつくつと肩を震わせた。 「ああ、そうだな。アンタそっちは清かったね」 「───なんだと?」 「神父なんてのはお互いカマ掘って慰め合ってるもんだと思ってたんだけどな」 くだけた調子で下世話な言葉を吐き、青年は顔を近付けた。思わず仰け反るように逃げると、腰が祭壇へと当たる。揺れた燭台の炎に視線を向けた瞬間、冷たい指が顎を掴んだ。 「───でもまあ、アンタそもそも童貞じゃないからな。……その割に、甘い水の匂いがするけど」 「なんの話だ」 「匂いだよ、………血の」 笑みに喉を震わせ続けながら、冷たい舌がゆっくりと唇の端を舐めた。逃げようにも固定された顎は動かせず、いつの間にか抱き寄せるように腰を支えていた腕はそう力を込めているようにも思えなかったが、それでもびくともしなかった。 は、と、冷ややかな呼気が掛かかる。 「………処女喪失もしたってのに、どうしてこんなに甘いんだろうな、アンタの身体」 「なにを言っ……、」 「匂いも味も極上だ。童貞処女に子供と聖職者の血は美味だと相場は決まっているが、それでもアンタみたいな生臭のは普通、臭くて堪ったもんじゃないんだけどな」 ロイは眼を瞠る。理解の色を見たのか、その眼がにやりと細まった。 「何か───言うことは、ないか?」 数刻前と似た問いを繰り返し、エドワードはゆっくりと体重を傾けた。がた、と祭壇が揺れる。ロイは伸し掛かる青年の肩へと手を掛けた。薔薇の香りにむせそうだ。 「お前───例の、猟奇殺人犯、」 「猟奇殺人?」 いかにも可笑しそうに嗤い、エドワードは冷ややかな癖に炎の下でもくっきりと赤い舌で、自らの白い唇を舐めて見せた。その動脈血の塊のような赤に視線を奪われた刹那、不意にエドワードは唇を吊り上げ歯を剥く。 「────な、」 笑みというよりも威嚇する獣のような表情で、唇の合間から覗いた───鋭い、牙が。 音を立てる勢いで伸びるそれに瞠目した黒い眼に、青年は満足げに瞳を細めるとふいに穏やかに表情を納めた。 「………解ったかい、神父さん」 ロイは引きつる息を呑む。脳裏に閃く霧の中の金色の眼が、見つけた獲物に笑むように薄く薄く細まるのを感じる。 「止……せッ!!」 驚愕に硬直したままでいたロイの首筋に、つう、と舌が触れた。反射的に押し退けようと肩へ掛けた手に力を込めるが、しかし見た目の細さに反して青年の身体はびくともしない。明らかに人間離れした腕力だった。 布地の裂ける音を立て、襟が強引に外される。 「………ああ、まだ残ってる」 囁きと共に穿たれたままのふたつの小さな傷口に舌が這い、ロイは微かな痛みに呻いた。 「人間ってのは不便だよな。こんな小さな傷がなかなか治らないなんてさ」 「貴様……ッ」 「じゃあ、今夜は反対側にしよう。傷口を広げるなんてのは趣味じゃないんだ」 反対側の首筋に鼻面を埋め、片腕でロイの自由を巧みに奪いながら右の指は僧服の合わせを解いて行く。ゆっくりと撫でられる度にぷつりぷつりと糸の切れる音がして、同時に下ろしたばかりのシャツの合わせも開かれかさぶたの残る膚に爪が触れた。その感触に、ロイは怖気を感じて思わず腕を伸ばし燭台を掴む。 「───離れろ悪魔め!!」 何を考えたわけでもなかった。けれど無意識に、その献火された炎にすがり青年へと押し付ける。 効果は劇的だった。 「─────、」 眼を瞠るロイの前で一瞬で火を移し燃え上がった青年は、声もなくふらりと一、二歩後退る。何故か熱さを感じない炎に包まれ、けれど確かに青年は燃えていた。 聖堂を赤々と照らす火の柱の中、青年の影は黒々と立ち尽くす。その眼だけが金を宿したままで、一瞬で瞼を失ったのか瞬きもなく凝視するその眼にロイは息が詰まるのを感じて思わず顔を歪めた。 |
2<< >>4
■2005/7/27
■JUNKTOP