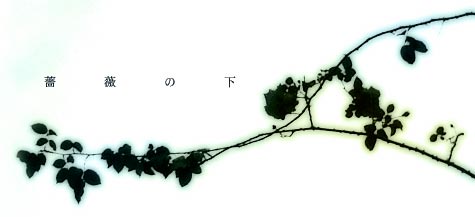
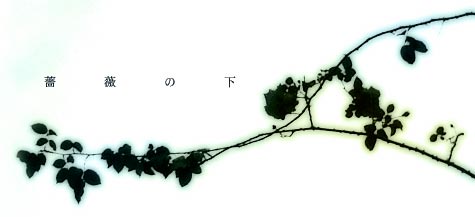
| アルフォンスの兄だ、と名乗ったその青年との出会いは鮮烈ではまるでなかったが、酷く印象的だった。 教会を辞するアルフォンスへ夕刻にはそちらへ行こうと言うと、出来ればすっかり陽が暮れてから来てくれ、と少年は申し訳なさそうに肩を竦めた。 「陽のあるうちは兄さんが出てこれないんです。あの……太陽の光に眼とか肌とかが弱くって。生まれつきの体質なんですけど、ほんとこう……ちょっとの光でもぶつぶつってすぐ赤くなって火傷になっちゃうから。うち、陽の光が全然入らない部屋って地下室の他はひとつしかないので、兄さん昼の間はそこから出て来れなくて」 それならば、と訪問するには少しばかり遅い時間につい昨日までは少年がひとりで住んでいた広い家の扉を叩いたロイの前に現れた少年は、教会に訪ねて来たときと同様の明るい笑顔で迎えた。 その少年の肩を抱き現れた青年は、陽の光に弱い、という言葉を裏付けるような真白な顔に、薄く、しかしどこか鋭い笑みを閃かせた。 「エドワード・エルリック。よろしく、マスタング神父」 差し出された手は手袋に包まれていて、握ると薄い布越しの体温は酷く低かった。ロイはその体温に思わず棺の中の遺体を連想し、その不躾な想像を慌てて振り払いよろしく、と笑顔で返す。その挨拶に青年は唇を歪めるような笑みを見せた。ロイはあまりいい笑い方ではないな、と考える。 仕事で各地を飛び回っているというからてっきり貿易商かなにかだろうと考えていたが、陽に弱いという特殊な体質やこの客商売に向かない笑み方を見るに、何か別の仕事なのだろう。 役者かもしれない、とふと思い、それから応接室へと招く青年のその身の翻し方や招く指先の動きや流されるどこか意味ありげな視線などの立ち振る舞いすべてが、妙に芝居掛かっていることにロイは気付いた。 「アルフォンス。………兄さんは役者か何かなのか?」 「え? いえ、」 「アル、ワイン持って来てくれよ。一番いいヤツな。解るだろ?」 前をとことこと歩く少年へと囁くと、返答をもらう前に振り向いた青年がそういって片目を瞑って見せた。その笑顔はどこか無邪気で、ロイへと向けられた皮肉で冷ややかなものとはまるで違う。 嫌われたかな、と考えながら、ロイは慌てるアルフォンスの背をぽんと叩いた。 「地下かい? 暗いから気を付けて」 「はい、あの、ゆっくりしててください! すぐ夕食の準備出来ますから」 「走るなよ、階段から転げたら事だ」 「はーい!」 快活な返事をしながらも燭台を手にぱたぱたと駆けて行く後ろ姿を苦笑しながら見送り、視線を返すと応接間からの明かりを半身に受け、影を濃くした青年がまるで仮面のように白くすべらかな頬に凍るような笑みを張り付かせていたのと目が合った。 「アルによくしてくれてたみたいだな、神父さん」 「………ああ、子供が一人でこんな大きな屋敷に住んでいるんだ、心配だろう。それにアルフォンスはいい子だしね」 「オレがずっと一緒にいてやれればよかったんだけどな」 「仕事ならば仕方があるまいよ」 エドワードは僅かに肩を竦めた。 「物分かりがいいことで」 もっと責められるかと思ったよ、とくつくつと喉を鳴らして笑いながら手で招いた青年について応接室へ入ると、何度か訪れたことのあるその部屋は以前来たときとは違う、分厚く豪奢なカーテンが窓に掛けられ、飾り棚に置かれた花瓶にはむせ返るほどの芳香を放つ薔薇が生けられていた。 「………これは君の趣味か?」 「どっち? カーテンか、薔薇か」 「カーテンは君の身体を気遣ったんじゃないのか? この仕立てはこの街の仕立屋のものだ、アルフォンスが用立てたんだろう。薔薇のほうだ」 「へえ、一目見て誰の仕立てか解るんだ」 「一昔前の都の流行だ。仕立屋の親父──ビルというんだが、彼はあの頃の流行ものが好きなんだよ」 ふうん、とエドワードはどこか感心したように頷いた。 「随分地域に溶け込んでいるんじゃないか、マスタング神父。アンタ都のひとだろう、なまりがない」 「なに、この土地に骨を埋めるつもりでいるんでね」 いい土地だよ、と笑うと青年は軽く片眉を上げ、答えずにただソファを勧めた。 「………目眩がしそうだな」 「ん?」 「薔薇の香りさ。気にはならないのか」 「ならないね、好きなんだ。オレたちの生家には薔薇園があったからな、アルも薔薇は好きだぜ」 「へえ……」 そういえば裏庭に這わせているのは薔薇だったかな、と顎を撫で、ロイはふと視線を感じて目を上げた。一人掛けのソファに高々と足を組んで座っているエドワードの、瞬きの少ない眼がじっと見つめている。そこでロイは初めてまじまじと青年を観察した。 どこか粗野な印象のある口調と表情を納めてしまうと、エドワードは酷く整った顔をしていた。鋭く切れ上がった眼は至高の金属と同じ輝きで、意志の強そうな眉は眼光を強調するように真っ直ぐに引かれている。やや太めの鼻梁は丁寧に整えられた彫刻のようで、しっかりとした顎は鋭く肉が削ぎ落とされていて一文字に引かれた大きめの口と相まって気性の荒さを示すかのようだ。 鮮やかな金の髪は産毛のようなアルフォンスのものとは違いしなやかで硬そうで、腰を過ぎるまで伸ばされ首の後ろでひとつにくくられている。その豪奢な金髪が影を落とす肌は灰色掛かるほどに白く、唇までもが石膏のような白だった。 白と金で彩られた、彫刻のような──青年。 ふ、と、その彫刻が唇を歪ませ嗤った。 「あんまりまじまじ見るなよ神父さん、照れるだろ」 「───いや、アルフォンスにあまり似ていないなと思って」 「両親ともに同じだぜ」 年も離れているし異腹だろうか、と考えていたロイの思考を読んだ訳ではないのだろうが笑みを浮かべたままそう言って、エドワードはゆっくりと身を起こした。 「見蕩れるのも結構だが、神父さん。………アンタのほうが綺麗だよ」 ぬっと腕が伸びたように感じて僅かに竦んだロイの頬に、差し伸べられた手袋に包まれた指が添えられた。慌てて視線を返すといつの間にかすぐ側にまでやって来ていたエドワードが薄く笑む。 「黒い髪に黒い眼に、白い肌か。……あまり見ない顔立ちだな。彫りが浅めで──子供みたいな顔だ」 布地を通してなお冷ややかな指がゆっくりと顔の窪みを確認するように鼻筋を辿った。なんだこいつは、と眉を顰め掛け手を払おうとして、ロイはふと眼が光に弱い、という話を思い出す。もしかすると酷く視力が弱いのかもしれない。こうして、触覚で相手を確認しなくてはならないほどに。 そんなことを考えてされるがままでいるロイに、エドワードはくっと僅かに声を洩らして笑った。 「男に触られて嬉しい?」 「そんなわけがあるか。これでも昔は女たらしで通っていたんだ」 「へえ、俗にいたのか」 「僧籍に入ったのは十代も終わりになってからだよ。我が家は聖職の家柄ではないんでね」 「ふうん? 親は」 「科学者だった。もう死んだ」 「縁者は?」 「いないね。天涯孤独というやつだ」 「だからこんな田舎に飛ばされた?」 ロイは軽く肩を竦め、無言で返した。不躾な質問をした本人は悪い失言だった、と軽く謝罪はしたものの、まるきり悪いとは思っていないようだった。 「なあ、アンタ」 指を引きソファへと戻りながら、青年がどことなく笑みのこもる声で尋ねる。 「何も言うことはないのか?」 「言うこと?」 怪訝に眉を顰めて尋ね返すと、エドワードは肩越しにロイを見た。その瞳が声と同様笑んでいる。 「ないなら、いいんだ」 「………よく意味が解らない」 「いいんだよ、気にすんな」 ならば口にするな、とちらりと揚げ足を取るようなことを考えて、ロイは慌ててその思考を取り消した。どうもこの青年と話していると聖職者の立場を忘れてしまいそうでいけない。 「………貪りすぎたかな」 「え?」 青年は嘲笑に似た笑みを閃かせ、いいや何でもない、と答えて酷く楽しそうに肩を震わせた。 |
1<< >>3
■2005/3/10
■JUNKTOP