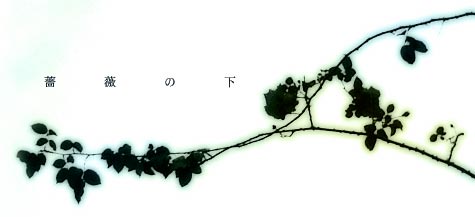
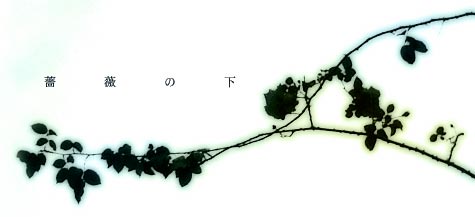
| 俄に湧き始めた霧が視界を白く煙らせる。 頬を撫でて行く湿度の塊にこれは早く帰らなくては髪も外套も湿ってしまうな、と考えながらロイは辺りを見回した。通りを二本行けば騒がしい歓楽街が広がるというのに噴水の止まった広場には人影はなく、ただガス灯の青い光が石畳に深い影を落とすのみだ。 空は暗く、星のひとつもないのにただ朧月ばかりが白々と浮いている。輝くことを忘れたようなその天の白い空白に、ロイはふと先ほど酒場で聞いたばかりの噂話を思い出した。 吸血鬼が出ると言う、噂。 ついに三駅向こうの街で犠牲者が出たとかで、明朝の勤めがあるからと席を立ったロイに、気を付けなよ神父さん、と気のいい主人が笑った。 悪魔は聖人を堕落させると言うからね。 ロイは神の杯を満たす葡萄酒ならともかくビールの味の解る聖人などいるものか、と同席した街の者たちと共に一頻り笑い、彼らの今夜の安らかな眠りへと祝福を祈り、そうして住処であるこの小さな街唯一の教会へと戻ろうとしている。 ふっと、霧に朧に滲んでいたガス灯が、ひとつ消えた。 そう認識した途端次々と消えて行く滲む光にロイはひとつ大きく瞬いた。白い月を僅かな光源に、霧は薄く発光している。 白い海底の、闇。 その闇の向こう、ふいに浮かび上がった細身の人影に、ロイは意識を奪われた。 髪の色すら解らない、闇と同化するが如く、けれど闇よりもさらに濃い人影は揺れもせずに真っ直ぐに立っている。あまりの気配のなさに、果たしてあれは本当に人間なのだろうか、とロイは訝しんだ。 そのロイの疑問が伝わったわけでもないだろうに、ふいに人影に気配が灯る。 ゆっくとり持ち上がった瞼の向こう、覗いたその瞳は爛々と輝く───黄金。 視線が吸い寄せられる。酷く強い吸引力を持つその双眸がゆっくりと細まった。 影と輝く瞳しか見えていないその人影が酷薄な笑みを浮かべた、と何故か気付いたところで、ロイの記憶は途絶えた。 身体の芯が痺れている。 酷く重い頭に昨夜はそんな呑んだだろうか、と考えながら、ロイは小さく呻いて額を抑えようと腕を持ち上げた。途端ずきりと走った外傷の痛みに、ぎくりとして眼を開く。眼前にある手首に、くっきりと掌の跡。 その腕に絡むのは僧服で、まさか着替えもせずに眠り込むほど泥酔したのかとロイは慌てて身を起こし掛け途端に下肢を駆け抜けた痛みに硬直した。 「な、に………?」 そろそろと身を起こし、鈍く痛み始めた身体に眉を顰めながら己の姿を眺め、ロイは呆然と息を吐いた。 引き裂かれた長く黒い僧服の合わせは全開で、ずれた外套はまだ肩に掛かり身体の下でしわくちゃになっている。下衣も辛うじて腰に引っかかっているという程度で、いつもは清潔な白いシャツのボタンはほとんど飛んでいて、露わになった胸部を中心に、細く長い引っ掻いたような傷が無数に走る。 その傷からだけではなく出血をしたのか、生白い肌には血痕が乾き、掌で擦るとぼろぼろと落ちた。首から下げたロザリオが薄く筋肉の乗った胸の上を滑りまるでそれだけが清潔であるかのように銀に輝く。 掌には泥と血。髪が砂でざらざらとする。地べたに伏したのか。 身体中が軋むように痛む。鼻孔を突くのは、血と、青い───獣の臭気。 ロイは眉を顰めた。 ロイは幼い頃から神の家へと住まっていたわけではなく、少年時代は日曜学校にすら滅多に顔を出さなかったほどの無信心者だった。だから早々に女を知っていたし、神学校に入ってからも何度か恋人を作りはしたから、生まれながらに神へと操を立てている者たちのように自慰の存在すら知らない、などということはない。だからこの臭気が何を意味するのかはよく解る。 よく解る、が、しかし。 知っていることと淫行に走ることは別だ、と眉を顰め痛む身体を引き擦り寝台から降り、転がっている長靴が片足分しかないことに気付いて、己の右足にもう片方が引っ掛かっているのに憮然とする。 その長靴を蹴飛ばし外套を解いて、ロイは裸足のまま石の床を踏んで浴室へと向かった。貧血か二日酔いか、ぐらぐらと目眩がする。 殴られたか床や壁に叩き付けられたか、打撲の痛みを訴える関節と、もっと直接的に引きつれる裂傷と引っ掻き傷に小さく呻きながらぼろに成り果てた僧服を脱ぎ捨てる。昼の光に露わになった内腿に残る血痕と白く乾きこびり付いたその跡が何があったのかを雄弁に語っていて、ロイは酷く憂鬱な気分になりながら鏡に掛かる布に手を掛けた。 女は悪魔だ、などと言いながら男色に走る僧侶も少なくはないが、ロイはその手の輩が理解できない。 女性ほどかぐわしくて柔らかな生き物もいないだろう、と聖職者にあるまじきことを考えながら鏡を覗く。 「─────、」 鏡の中の青白い顔が瞠目した。光を吸い込んでしまう黒い瞳が驚愕にみるみる薄く灰色へと色を落とす。 ロイはそろそろと手を持ち上げて首筋を押さえた。ちくりと走る小さな痛みに僅かに身体を強張らせ、ゆっくりと、震える指先でそれを辿る。 胸までを血に汚したその小さな傷は細く穿たれたふたつの穴で、出血は止まっているもののまだぽかりと口を開けたままだ。 ───吸血鬼が出る、という、噂。 馬鹿な、と口の中で呟いてロイはいささか乱暴に布を引き鏡を覆った。 そんな馬鹿げた話はない。吸血鬼など存在するはずがなかった。ただ吸血鬼を模した猟奇事件が大都市を中心に頻発していると、それだけのことだ。 (………猟奇殺人犯が同性愛者だとは知らなかった) 記憶がないのが疑問ではあったが、とにかくこの街にその犯人が逃げて来たか、そうでなければ模倣犯が出たのだろう、と溜息混じりに強引に結論付けて、ロイはシャワーのコックを捻った。冷たい水に身を打たせ、下げたままのロザリオを握る。 つむじから冷水を浴びながら瞑目すると、身体の芯にまとわる痛みが増した気がした。 「神父さまー。いらっしゃらないんですか? 神父さま」 ごんごん、と扉を叩く音にロイは慌てて襟の高いシャツのボタンを留め痣の残る手首を隠すようにきっちりとカフスを嵌めながら、まだ鈍い痛みを訴えている身体を叱咤し勝手口へと向かった。 「神父さまー」 「アルフォンス? 今鍵を開けるから」 言いながら静かになった扉から鍵を抜き開くと、ぽつんと立っていた十二、三歳ほどの少年があからさまに安堵した笑顔でロイを見上げた。 「良かった! もうとっくにお昼も過ぎてるのに教会が開かないから、具合でも悪いのかと心配しました」 「………昼?」 「もう三時近いですよ」 眼を瞠ったロイにふいに眉尻を下げて小首を傾げ、アルフォンスは抱えていた籠を差し出した。 「あの、これ、パンなんですけど。ボクが焼いたんです。神父さまにどうかなって」 「あ、ああ……有難う」 「………大丈夫ですか? 顔色悪いですけど……もしかしてほんとに具合悪くて寝てたとか」 「いや、昨日ちょっと……呑み過ぎてね」 「ええ? 二日酔いですか?」 珍しい、と光の加減で金にも見える黄みの強い茶の眼を瞬かせるアルフォンスに苦笑して見せて、ロイは少年を招いた。 「お茶でも飲んで行きなさい。悪かったね、聖堂も開けずじまいで」 「いえ、それはいいんですけど……でも本当に大丈夫ですか?」 「ああ、問題ない」 それならいいけど、と頷いて、アルフォンスはあの、とロイの袖を引いた。 「どうした?」 「………あの、神父さま。今日、ボクのうちで夕食をどうですか?」 「構わないが……君の誕生日か何かだったかな?」 「いえ、そういうんじゃないんですけど、あの、兄さんが帰って来てて」 はにかむ少年にロイはおや、と瞬いた。 「仕事であちこち飛び回っているんだったかな?」 「はい。でも一段落したからって……二年ぶりですよ! 引っ越して来てボク置いて出掛けて、そのまんま一回も帰って来てくれないんだから」 忙しいのは解るけど、と寂しさを隠した拗ねた顔で愚痴をこぼす様を幾度も見ていたロイは、むくれたふりをする少年の金の短髪をぽんと撫でた。 「そうか、それは是非挨拶をしなくては」 「神父さまは会ったことはなかったですよね?」 「君が私のところへ挨拶へ来たときにはもう出てしまった後だったろう? 一度も見掛けたことはないな」 ですよね、と頷いて、アルフォンスはへへ、と僅かに頬を紅潮させて笑った。 「神父さまにはずーっとお世話になってたし、是非兄に紹介したいんです」 嬉しさを隠せない様子にロイは瞳を細めて笑んだ。 「では迷惑でないのならば、お邪魔させてもらおう」 「迷惑だなんて! 兄さんも会いたいって言ってるんです。だから」 「おや、君の兄さんは私のことを知ってるのか?」 「あ、えっと………ボクが手紙で何度か神父さまの名前出したから……それで、アルが世話になってるひとなら挨拶しないとな、って」 夕食に誘ってこいって言ったのも兄さんなんです、と笑う少年には両親の記憶はないのだと言う。親代わりでもあった兄が好きで堪らない様子に、ロイはぐりぐりとアルフォンスの頭を撫でた。 この子が、毎日朝早くから兄の無事を祈るために通っていたことを知っている。 「兄が無事に戻って良かったな、アルフォンス」 アルフォンスは満面で笑み、こっくりと頷いた。 |
>>2
■2005/3/7 薔薇の下で交わした会話は秘密。
『薔薇の下』はアイロイさまで行われた吸血鬼祭り参加作品です。吸血鬼エドワード×神父ロイの設定等の著作権は、お祭りに参加された皆さまに帰属します。
■JUNKTOP