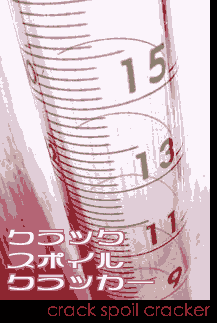
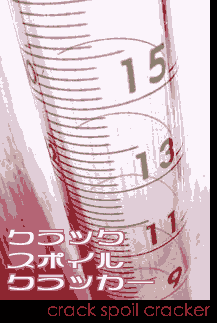
外は嵐。 あつらえ向きに照明の切れかけている、まだ午後も浅い時間だというのに薄暗い廊下をエドワードは怒気も露わに足音荒く歩いていた。握り締めた右手がぎ、と響く。 悪天候に機械鎧との接続部が鈍く軋み、その鈍い痛みが幻肢痛を引き起こしエドワードの苛立ちは否応なく増した。 ───あなたのせいではないのよ。 優しい女性士官の宥めるような声が耳に蘇る。その一瞬だけ僅かに足を弛め、しかし直ぐにぎり、と奥歯を噛み締めてエドワードは再び早足に目的の部屋へと向かって歩き出した。 失くした手足の痛みは冷えとともに背を首を昇り、もう随分と前から頭痛も酷い。軽く眩暈がして、頭に充分に血が通っていないんだな、とどこか寝惚けたような理性が呟いた。 (オレのせいだ、中尉) エドワードはリザの前で呑んだ言葉を胸中で呟き、眦の吊り上がった眼を僅かに細めた。 頬に大きく絆創膏を貼った、煤と泥と血で汚れた軍服を纏った綺麗な顔を思い出す。多分その汚れた軍服の下にはあちこちに包帯が巻かれているのだろう。 ばたばたと駆け回る軍人たちも皆怪我を負っていて、それを目にしたアルフォンスが自分のせいだと消沈するのをアルのせいじゃない、と慰めたエドワードだが、それでも己の失態まで慰めてしまうつもりは毛頭なかった。 テロリスト集団を捕らえた、までは良かったのだ。 また大佐の手柄になっちまうな、と毒突いて、アルフォンスと笑い合った、そこまでは。 ただ一人、爆弾を抱えたテロリストを、取り逃がしたことに気付くまでは。 爆弾を抱えた男は自爆して死んだが、その際テロ鎮圧のために駆け付けていた軍の本部近くまで忍び込んでいて、お陰で士官が一人と下士官が四人死亡、重傷者多数、軽傷者に至ってはまだ正確な数は把握できていないほどで、たった二人でテロリスト集団を相手に市民への攻撃を防いだエルリック兄弟を責める者はなかったが、それは単に、彼らの上司がマスタング大佐である、というそれだけの理由によるものにすぎない。 士官が死んだのだ。エドワードのよく知るあの男が指揮官でなければ、いくら民間人とはいえ軍属のエドワードが責任を問われずに済むわけはない。 恐らくは、エドワードの代わりにあの男がその失態を被ったのだろう。 くそ、と呟いた声は平たくて抑揚がなく、エドワードは胸の中の怒りに似た感情を一欠片も吐き出すことが出来なかった。それどころか口を開いたことで酸素を得た感情の炎がより激しく燃え上がった気がして、乾いた唇を舐め頬を歪める。 ───リザや、ハボックや、あの男が死んでも、おかしくなかった。 リザがあの程度の怪我で済んだのは運が良かったとしか言いようがない。司令官のくせに現場に出たがるあの男だからわずかに本部から離れていて、そのため爆発の中心には巻き込まれずに済んだと、ただそれだけのことだ。 大佐も無事だから、安心してあなたも今日は休んで。 リザの宥める言葉にうんと頷いて、けれど休める気などしなかったから、無理を言って資料室の鍵を借りた。ばたばたと忙しい軍部内で呑気にデスクワークに勤しむ者など今日はないから、資料室は貸し切りだろう。 少し、頭を冷やす必要があると思った。 宿へ戻って休めとアルフォンスを送り出し、エドワードはこうして一人、人気のない廊下を資料室へ向かって歩いている。 程なく目的地へと辿り着き、鍵を差し込み回してノブを引いたエドワードは眉を顰めた。どうも鍵を掛けてしまったらしい。 ということは、先客がいるのか。 誰にも会いたくないのに、と溜息を吐きながら、エドワードはもう一度鍵を差し込んで解錠し、扉を開いた。 雨と風の音が酷い。 資料室は壁が薄いのか、他の部屋よりも一層嵐の音が響くようだ。その騒音の中に時折雷鳴も混じり始めていて、事後処理が進まんな、と部屋の一番奥の書棚の陰で、ロイは溜息を吐いた。開いたファイルの薄いページが息にふっと踊る。 ロイは包帯の巻かれた手でそれを押さえ、爪の間に血と泥がこびり付いたままの指で文字を辿った。ちかちかと瞬く照明は嵐の影響か、単に切れかけているのか。 どうにも読みづらいな、とまた溜息を吐き、二冊目のファイルを引き出して一冊目の上で広げる。傷を負った左肩に分厚いファイルの重みが掛かり、僅かに痛んだ。 両手でファイルを支え、ロイは目を眇めて瞬く明かりにちらつく文字を追った。過去の犯罪者のデータだ。今回エルリック兄弟が捕らえたテロリストたちの中にいくつか見た憶えのある名が混じっていたような気がして、リザに休めと追い出されたのをいいことに資料室に籠もり始めてもうどれだけ経ったのか。疲労に萎えた足は棒のようだが、なかなか目的のファイルは見つからない。 誰かに手伝わせればよかった、と考えながら、ロイはページを捲った。 ふいに、嵐の音に混じりこつり、と微かな足音がした。 「ハボック少尉?」 迎えに来るならハボックかリザで、リザは今自分の代わりに指揮を執っているのだから前者だろう、と見当を付け、ロイは振り向かないままに続けた。 「ちょうどよかった、どうも一人では手に余ってな。手伝ってくれ。ここは大体見たから、お前はそっちの書棚を探せ。10年前からので充分だ。a、d、k、r、t、それぞれ見ろ。対象のファーストネームはアルマン、アンドル、ダグラス、キム、ケイト、ランダル、トロイ、以上。即掛かれ」 いつもの調子で命令を下し、文句が返ってくるものだと思っていれば口どころか気配すら動かず、ロイはファイルから顔を上げた。 「ハボック?」 振り向き、ぴたりと動きを止めてひとつ大きく瞬く。 「………鋼の。帰って休むようホークアイ中尉から言われなかったか?」 鋭い金の眼で瞠目し、酷く険のある強張った表情で身動きもせずに見つめてくる子供にロイは眉を顰める。 「どうした?」 「………、……んだよ、全然大丈夫じゃ、………」 「え?」 低く呟かれた声に雷鳴が重なり消えた。思わず聞き返したロイに答えず、子供は唐突にがつがつと大きく踵を鳴らして歩み寄ると右腕を振り上げ軍服の襟を掴んだ。そのままぐいと突き飛ばされる。 いつもなら踏み止まるところだが、ずきりと走った痛みに僅かに息を詰めた隙に足下がふらつきロイはそのまま大きくよろめいた。ごつ、と硬い音を立てて分厚いファイルが落ち、無意識に支えを求めて伸ばした指が書棚を擦り勢いを殺したが、それでも結構な衝撃を背に受けて呻き、ロイは自分が無様に倒れたことを知った。 「何、をするんだ君は!」 怪我に響く痛みに顔を歪めて吐き捨てるように文句を言いながら見上げると、まだ胸倉を掴んだままロイを跨ぎ覆い被さる鋭い眼と視線が合った。 黄金の眼が、冷たく燃えている。 「鋼の?」 ちりちりと耳鳴りのように警鐘が響くが、それは戸惑いに掻き消された。 ロイは子供の銘を呼び包帯に包まれた手を伸ばしてその額に指を触れる。 「どうした? 酷い顔だ」 子供の生身の手がその指を強く掴んだ。容赦のない熱い掌に、痛みが肘まで電流のように駆け抜ける。ロイは眉を顰めた。 「怪我人なんだ、もう少し手加減を───」 握られた右手が床へと縫い止めるように強く押し付けられた。途端先程の比ではない痛みが走り、傷が開いたか、と舌打ちをしたロイの眼前に金の帳が下りる。 「────ッ!?」 押し付けられた唇に瞬く間もなく侵入して来た舌が歯列を割る。慌てて押し返そうとすると強く唇を噛まれぱっと血の味が散った。その刺激に唾液が分泌され口内全てが血の味とエドワードの舌に犯される。 ロイは編んだ金髪を掴み強く引いたが、怪我を負った左肩を鋼の掌に押さえつけられ身を強張らせた。さあっと薄絹を引くように視界に薄闇が掛かり、どっと冷や汗が浮く。縮み上がった舌を子供の熱い舌が絡め取り引き出し、がり、と噛んだ。 つ、と口の端から流れた唾液が頬を伝い落ちた。血が混じるだろうから、後できちんと拭き取らなければ目立つな、とどこか遠い意識で考えて、ロイは微かに震える手でもう一度掴んだままだった金髪を引く。 今度は素直に去った舌と離れた唇が、しかし唐突に首に触れ、喉仏を強く噛んだ。 強制的に声と息を殺されロイの身体が強く引き攣る。髪を離した手の爪が切羽詰まった動きで子供の頬を掻いたが、エドワードは構わず喉に歯を立てたまま軍服の合わせを力任せに開いた。拘束されたままの右手は酷く痺れて感覚がない。 「………がッ、ね……ッ」 途切れ途切れに苦しい息に交えて銘を呼ばれ、エドワードはようやく牙を収めてゆっくりと噛み跡を舐めた。舌に大きく上下する喉の動きを感じる。ひゅう、と木枯らしのような音を立てて空気を貪るロイの胸に這わせた鋼の手にはその鼓動は響きはしないが、恐らく早鐘を打っているのだろう。 開いたシャツの下に、血の跡を残したままの膚と包帯が覗く。 その乾いた血を舐めるように胸に唇を落とし生身の左手は包帯の巻かれた大人の指に絡めたまま鋼の右手で腰を撫で、逸る仕草で軍服のベルトへと触れると自由な片腕が伸びて来て前髪を強く掴んだ。 エドワードは躊躇わず、鋼の右腕を上げロイの左肩を強く押し付ける。 「うぁ……ッ」 ひび割れた声が喉を絞るような悲鳴を上げた。エドワードの髪を掴んでいた手が震え緩み、ロイの意思とは無関係に床へと落ちる。青醒めた汗の浮く顔を一瞥し、エドワードは素早くロイのベルトを外し下着ごとボトムをずらした。 「鋼の…ッ、お前、なにを、」 閉じかける目を無理矢理開きひゅうひゅうと掠れる声で嵐に掻き消されぬよう、同時に室外へ洩れぬよう囁くように怒鳴ると、子供の金の双眸がほんの一瞬射抜くようにロイを見つめた。 瞬きもないそれはどろどろに熔けた金のように滑らかに熱く滾っていて、ロイは小さく息を呑み、痛みに震えながらも制止のために上げ掛けていた左手を再び落とした。 ロイの諦観を感じたのか、エドワードが右手を解放した。感覚のないその手の指を軽く曲げるとびり、と痛みが走る。縫合してもらったばかりだというのにどう言い訳をしたらいいんだ、とまだ上手く吐けない息で小さく溜息を吐くと、内股にひやりと機械鎧が触れた。 「おい……鋼の。言うだけ言っておく、が……ここは………ッ!?」 前戯もなく最奥に触れた鋼の指に、ロイは持ち上がらない両手での制止を諦め咄嗟に大きく息を吐き身体を弛緩させた。一瞬遅れてびり、と強い痛みと共に無機の温度が無理矢理押し込まれ、口を突きそうになった悲鳴を歯を食い縛り止める。 「………ッ、」 びく、と跳ねた身体を宥めもせずに、子供はほとんど脱がされていない軍服に包まれた足を無造作に持ち上げ一度大きく鋼の指を捻るように回して抜いた。 もう疾っくに赤く染まっている包帯の巻かれる右手の指が鈎のように曲がり強張る。左手はがり、と掃除の行き届かない床を擦りながら、ぎこちない動きで持ち上げられ、赤いコートに包まれた子供の硬い右肩を掴んだ。 「鋼の…ッ、止…せ、まだ……ッ」 「煩い」 嵐に消える声で低く呟き、エドワードは機械鎧の肩ごと掴む左手をそのままに全く解れていない秘所へと熱を押し付けた。ぎ、と掴まれた金属を被せた肩が軋み、コートに強く皺が寄る。 「────……ッ!!」 無理矢理身体を押し開かれる激痛に反らせた背が浮く。咄嗟に血に染まる包帯の右手が歯を食い縛ることも出来ない口元を覆い、切れ切れに洩れる悲鳴を殺した。 |
>>2
■2004/10/27
■NOVELTOP