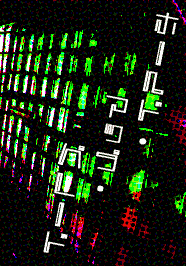
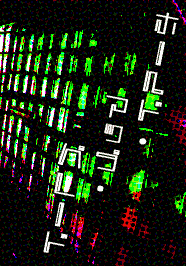
「アンタ結構人気あるんだな、……おばちゃんに」 市場を通り過ぎる間に何度も働き者のおばちゃん方に声を掛けられそのたび笑って手を振るロイに、エドワードが感心しているのか呆れているのか解らない声で言った。ロイは「女性には優しいんでね」と嘯き、雑貨屋の店先に繋がれていた犬に手を振る。犬はぱたぱたとふさふさした尻尾を振って三人を見送った。 「……今のは雌犬ですか」 「そうだね。この間子犬を四匹産んだんだが、そう言えば貰い手は付いたのかな。あそこの主人に一匹どうだと言われていたんだが」 「歳も関係なきゃ動物でもいいのか。犬にまでたらしかよ」 「失敬な」 それほど狭くもない路地までひとが溢れかえっている。その中を軽口を叩きながら通り抜け、住宅街を進んでやがてロイのアパートメントへと到着した。 「官舎じゃないの?」 「ああ。軍の管轄下では落ち着いて研究も出来なさそうなんでね」 「研究してる時間はあるんですか?」 「ない」 「意味ねぇし」 ロイは鍵を開ける。招かれるままに兄弟はアパートメントへと踏み込み、薄暗い廊下にただよう埃のにおいに気付いたエドワードがくんくんと鼻を鳴らした。 「あ、本のにおいかこれ。掃除してねーのかと思った」 「いや掃除もあまりしていないんだが」 「うっわ………」 ロイに続いて居間へと進んだアルフォンスは絶句する。 テーブルにもソファにも床にも本が積まれ、そこここに書き掛けのメモやどう見ても軍のものではないかと思われる書類(いいのか持ち出して、とはエドワード)が散らばる。食べ物が散らかっていないせいでさすがに生ごみの臭いはないが、これは相当の間掃除をサボっているんだな、と兄弟は顔を見合わせてどちらともなく頷いた。 「あのさ……大佐」 「うん? ああ、座っていたまえ、夕食を作るから。……そういえば君、シチューは食えるのか? 牛乳を使うが」 「あ、兄さんってシチューだと牛乳入ってても食べられるんです」 ほう、とわざとらしく驚いた顔を見せてロイはにやにやと笑う。 「では積極的にシチューを食べることをお勧めするよ、鋼の。少しは背が伸びるかもしれん」 「余計なお世話だ!! つか、どこに座れってんだよ」 「適当に。ソファの本を床に下ろしていいから」 「………散らかし過ぎです大佐」 「仕方がなかろう、この頃まともにここに帰れていないんだ。暇になったら片付けるよ」 「いつ暇になるんだよ、司令官……」 まあそのうちな、と先程と似たようなことを言ってロイはキッチンへと消えた。エドワードはぶつぶつと文句を言いながら床へ本を下ろし、どかりと座り心地だけはいいソファに沈む。 「いー部屋なんだけどなあ」 「家賃高そうだよね」 「宝の持ち腐れだよな」 ひそひそと顔を寄せて囁き合い、エドワードは積まれている本を無造作に一冊取って開く。 ぱらぱらと捲り、興味のある箇所でも発見したのかふと真剣に読み出した兄にああもう没頭しちゃってる、とかしゃりと首を傾げ、アルフォンスはキッチンへと顔を向けた。ごとごとと棚を開ける音がする。 「大佐、何か手伝いますか?」 キッチンを覗いてそう言うと、鍋を取り出したロイが振り向いて首を傾げた。 「料理が出来るのかね?」 「いえ、全然。でもじゃがいもの皮くらいは剥けます」 「ふむ。じゃあ剥いてもらおうか」 アルフォンスははい、と頷いてバケツを引き寄せ椅子に座り、じゃがいもとナイフを手に取った。 「キッチンは片付いてるんですね」 「使わないからな」 「……使わないんですか」 「家に帰る暇がなかったから使う暇もなかった」 言いながらもロイは野菜を切って行く。アルフォンスは料理人や主婦のように手際がいいわけでもないのに妙に無駄のない動きを感心してちらちらと眺めながら、じゃがいもの皮を剥いた。 「大佐って結構料理上手いんですか」 「いや、普通だろう。何故?」 「いえ、なんだか手際がいいので」 「士官学校時代に教官にこういうのが好きな御仁がいてな。彼の教え子は大抵呼び出されては料理の下拵えをさせられたから、まあこの程度はヒューズも出来る」 「へえ、そうなんだ。面白い先生だったんですね」 ロイはくつくつと喉を鳴らした。 「士官学校に行ってみればそんな呑気なことは言っていられないぞ。起床から就寝まで規則規則で息つく間もない」 「……ボクには軍人は向かない気がします……」 言いながら皮を剥き終え、アルフォンスはナイフを置く。 「えっと、後は……」 「ホワイトソースでも作ってみるかね」 「え!? い、いや、だって難しいんでしょう?」 「そうでもないさ。焦げないようにきちんと掻き回していれば出来る」 「で、でもボク、味見もできないし……」 「ホワイトソースで味見はしなくていいし、必要だとしても私がいるだろう。私はパイの生地を伸ばすから」 ほら、と鍋と木べらを渡されてアルフォンスは思わず姿勢を正した。 「が、頑張ります!」 「失敗してもまた作ればいいから、気楽にやるといい」 料理は科学だよ、と澄ました顔で嘯くロイに、アルフォンスはあはは、と笑った。 「でも化学実験みたいにして作った料理って、お母さんとかの料理には全然かなわないんですよね」 「あれは不思議だな。あれかね、愛情の差というヤツか」 「そうかも。食べてくれるひとのことを思って作るんだって、いつも母さんが」 ふ、とどこかへ吸い込まれるようにアルフォンスの語尾が消えた。その気まずさにはっとして、アルフォンスは首を傾げながらバターを火に掛け木べらで伸ばす。 そんなアルフォンスに気付かないのか、背を向けたまま生地を伸ばしているロイがそう言えば、と悠長な声を掛けた。 「君たちのお母さんはどんなひとだったんだね」 「………え、と」 アルフォンスは房飾りを揺らして顔を上げ、壁に掛かったフライパンを見、再び鍋へと視線を落とした。 「優しいひとでしたけど、怒ると怖くて、……えっと、ボクらの前ではいつも笑ってるひとでした。絶対泣いたり落ち込んだりしなくて、凄くボクらを愛してくれた。父さんがいなかったから、余計にそうだったのかなって思うんですけど」 「ほう」 「身体も丈夫なひとで───あ、ええと、ボクらが気付かなかっただけで無理してたのかもしれないんですけど、……ていうか、無理してたから倒れるまでボクらは気付いてあげられなかったんですけど」 「親は子供には心配を掛けたくないと思うものだよ」 「そうかもしれないんですけど……」 アルフォンスは小麦粉を足して練りながらかしゃん、と俯いた。 「でも、父さんはいなかったんだし、ボクらは三人だけの家族だったんだから、……頼って欲しかった、です。無理なんかして欲しくなかった。辛いって言ってくれればよかったのに」 「言えないこともあるさ」 「だけどボクらは悲しかったんです」 悲しくて悲しくて、悲しみを癒す方法がよく解らなくて、だって今まではずっと悲しくて苦しくて怖いときには母のエプロンを握って震えて泣いていたのに、もうその優しい手はなくて、だから。 「───ばっちゃんには物凄く叱られました」 「ロックベルさんか」 はい、と頷いて、アルフォンスは小さく笑う。 「どうして泣きつかなかったのかって。どうして相談しなかったのかって。……大佐、ボクらは……母さんだけじゃなくて、ばっちゃんもウィンリィも友達も、みんなを裏切ってしまったんです。ボクらを大事にして心配してくれるひとたちが、ボクらには見えていなかった。ボクらは安易な支えに逃げたんです。錬金術が救いだと思ってた。たくさんの本と理論が絶対に正しくて、それは大事なひとたちがくれる心配よりも、ずっと真理に近いんだと思ってた」 「……錬金術師なら一度は通る道だな、それは」 アルフォンスは思わず振り向いた。いつの間にか作業を終えていたらしいロイは、テーブルに寄り掛かり腕を組んでアルフォンスを見つめていた。 「大佐も、そういう時期があったんですか」 「あったよ。人間と付き合うよりも、一冊でも多くの本を読んだほうが自分の糧になるのだと酷い思い違いをしていた時期が」 「………大佐は、後悔したことはあるんですか」 「あるよ、痛烈なヤツをね」 ほら、焦げるぞ、と指差されてアルフォンスは慌てて木べらを動かした。 ロイに手伝われて牛乳を加え、別の鍋で煮ていた材料と合わせて指示されるままに調味料を加える。気が付くと指示はあったものの結局アルフォンスが大体作ることになってしまっていて、少年はかぽ、と鍋に蓋をしてしばしぽかんと宙を見つめた。 「………ボクにシチューが作れるとは思いませんでした」 「結構簡単だろう」 「味見が出来ないのがネックですけど」 「分量と火加減を覚えておけば大丈夫だ、そう大きく味は崩れない」 それに君は勘が良い、と笑うロイに、アルフォンスは有難うございます、と肩を竦めた。 「あとはどうするんですか?」 「耐熱容器にシチューを注いで生地を被せてオーブンで焼いて、終わりだよ」 「………そう言えば、オーブンの調子が悪いとか言ってませんでしたっけ」 「ああ、ちょっとね、ときどき火が消えてしまうんだ」 「凄く壊れてるじゃないですか。兄さんに直してもらえばいいですよ」 ちょっと待っててください、と言い置いてアルフォンスは居間を覗く。 「兄さん、ちょっと来て。兄さーん」 おーい、と声を掛けて肩を揺するが、どうも活字に没頭しているらしいエドワードは顔も上げない。アルフォンスは溜息を吐いてチョークを取り出し、キッチンへ戻った。 「ダメです、兄さん本に夢中になっちゃって」 「ああ、じゃあいい。運が良ければちゃんと出来る」 「運任せでせっかく作ったご飯無駄にしないでください。ボクが直します」 どいてどいて、と大人を追いやり、アルフォンスは跪きオーブンの蓋へとカリカリと錬成陣を書いた。腕を組んだロイが感心したように覗き込む。 「上手いものだ」 「ていうか大佐、どうして自分で直さないでほっとくんですか」 「固体錬成は面倒臭い」 「いや……直すだけでしょ……」 「オーブンの図面も見たことがないし」 「き、基本でしょ? 台所用品も農具もラジオも」 「全然直したことがない」 「……………。……大佐、都会のひとなんですかもしかして」 「地方都市出身だ」 「都会のひとなんですね……」 はー、と溜息を吐き、アルフォンスはチョークをしまって手を翳した。途端ばしっと青白い稲妻が弾け、古びたオーブンが新品の艶を取り戻す。 「はい、いいですよ」 「有難う」 「どういたしまして。宿代です」 「おや、こき使った上に宿代までもらっては過剰徴収だな」 「あれ、そっか、そうですね」 あはは、と笑ったアルフォンスに、オーブンへと器を入れながらロイはふむ、と呟いた。 「では夕食が済んだらちょっと出掛けないか。パレードを見に連れて行ってやろう」 「え、けど、待機してなくていいんですか」 「いいさ。そんなに長く留守にするわけでもないし、うちの部下は優秀だからね、私がいなくてもなんとかするさ」 「い、いいんですかそれで」 「じゃあ何かね、君は勤務時間外も私にずっと家で待機していろと言うのかね」 「いやそういうわけじゃないんですけど……」 アルフォンスはあわあわと両手を振り、ぺこんと頭を下げた。 「えっと、じゃあ、お願いします。……ボク、ちょっとパレード見たかったし」 独りで散歩に行こうかと思っていたんです、と小さく笑うアルフォンスに、水臭いな、とわざとらしく唇を曲げ憤慨して見せて、ロイはオレンジを手に取った。 「さて、鋼のはどうすれば食事の時間だと気付くのかな」 「あ、じゃあボク、本奪って来ます」 「壊さないでくれよ、私の本だ」 既に居間へと戻り掛けたアルフォンスから、はーい、と可愛らしい返事が届く。 ロイは薄く笑い、オレンジを剥くべくナイフを手に取った。 |
1<< >>3
■2004/9/4
話が逸れる逸れる逸れる……。
まだ全然本題に入ってません…。
■NOVELTOP