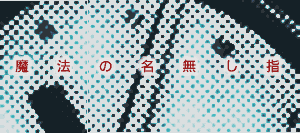
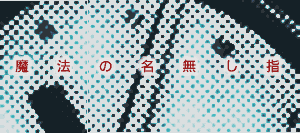
「何か言うことはあるか」 エドワードは眉を寄せる。一瞬「謝るんだよ」と言っていたアルフォンスの声が耳に響いたが、それを無視して目を逸らす。 「別にねーけど」 「そうか」 ふ、と溜息混じりに返されて、なんだか胸を掻き毟られた気がした。 どうしてこの男の些細な行動にこうも神経を逆撫でられるのだろう。 「なあ、鋼の。昨日の話なんだが」 「…………」 「一度口に出したことを反故にするのも申し訳ないんだが、やめようかと思うんだが」 いいか、と尋ねた声は微塵も乱れず優しげですらあって、エドワードは両手を強く握り締めた。 「………別れるってこと」 「いや」 短い否定の言葉にエドワードはそろりと目を上げる。 「じゃあ、なんだよ」 「君に嘘を吐いてやる、という話だ」 伸びて来た手がエドワードの額へと掛かる金髪を払う。視界が僅かに晴れて、エドワードは目を細めた。 「……やっぱり別れるって話じゃねーの」 「違うよ」 「でも、好きじゃないってことなんだろ」 「違う」 低い声が思いがけず真剣に響いて、エドワードは瞬きを忘れた。ロイは相変わらず光のない眼でエドワードを見下ろしている。 「………君に嘘を吐くのはなかなか気分が悪いんだ」 ふ、と、微かに嘆息しながらロイは続けた。 「君は私を嘘吐きだと言うが、君の気持ちに応えるときに嘘を吐いたことはないよ」 「───嘘だ」 「本当だ。どうして嘘だと思うんだ」 「だって、」 エドワードは言葉に詰まる。ロイは続きを待っている。 「………だって、言ってくれないだろ、何度聞いても」 「嘘を吐きたくなかったんだ」 「本当のことを言えばいいだろ。嫌いなら嫌いって」 「嫌いじゃない」 「じゃ、迷惑だって言えばいいだろ」 「迷惑ならそもそも家に招き入れたりしない」 「それじゃ、なんなんだよ!」 「そこで癇癪を起こすな」 軽く頬をつままれエドワードはむっとむくれる。 「子供扱いすんな」 小さな苦笑が返され、エドワードはよりむくれた。 「まあそう怒るな」 「じゃあはぐらかさずに答えろよ」 「………質問をどうぞ?」 どこかおどけた風に首を傾げ、わずかに唇に笑みを掃いたロイをエドワードは険しい顔をしたまま睨んだ。 「ちゃんと答えろよ」 「ああ」 「はぐらかしたらマジで怒るぞ」 「もう怒っているじゃないか。いいから訊きたいことを訊け」 エドワードは大きく息を吸い、丸めていた背を伸ばし精一杯虚勢を張るようにロイを睨んだ。 「オレのことをどう思っているのか、言え。好きか嫌いかはっきりしろよ」 緩やかにカーブした唇が、微かに笑みを含んだ息を吐いた。細められた眼がエドワードを見つめる。 「───好きだよ」 息を詰めたエドワードの視界で、ふとロイが視線を落とした。くく、と笑みが洩れる。 「こんな風に告白をしたのなんて10代の頃以来だぞ、鋼の」 馬鹿みたいに照れるな、と赤くなりもしない顔で言って、ロイは視線を伏せたままの目元を手で覆った。エドワードは思わず身を乗り出し、その手を掴む。黒い双眸がエドワードを見た。 エドワードはごくりと喉を鳴らす。 「───もっかい言って」 ロイは思わず、と言った様子で破顔して、掴まれた右手はそのままに左手を伸ばしエドワードの金髪をくしゃくしゃと掻き混ぜるように撫でた。あからさまな子供扱いではあったが、そのわずかに冷たい手がやけに優しかったのでエドワードは黙って好きにさせる。 「好きだよ。君の期待する好意にどれほど近いのかは解らないが、取りあえず、相当に」 「相当ってどのくらい」 ロイは一瞬迷うように瞬いたが、直ぐに視線を戻して幾分か笑みの失せた顔で答えた。 「………君が去ってしまったら寂しいよ」 エドワードは恋人を見つめた。どこか飄々としたその顔は言葉にそぐうものではないが、それでも多分、嘘ではない。 ───嘘ではない、と思っていたい。 エドワードは乾いた唇を舐め、口を開いた。 「……オレは、アンタが拒まない限りアンタの元を去ったりしない」 「アルフォンス君はどうする」 「アルを手放すわけがねーだろ。アイツはずっとオレのものだ」 「アルフォンス君のために去らねばならないとしたら?」 強く輝く金の瞳を、久しぶりに見た、とロイは思った。 エドワードは鋭く切れ上がる大きな瞳を開いたまま、にやり、と唇を歪めて強気に笑む。 「どっちも獲る」 「………とれないとしたら」 「それでも獲る。オレが欲深だってこと、アンタはよく知ってんだろ?」 「そうだな……」 ふ、と微笑んだその笑みが苦笑であることに気付き、エドワードは眉を寄せた。 「なんだよ。嬉しくないのか」 捕らえたままだった右手がエドワードの指を軽く握る。 「鋼の。私は永久に君に付き合ってやるわけにはいかないんだ。好きだから共に在れる、というわけにはいかない。気持ちが共にあれば共にいられるというのはしがらみを持たない子供の幻想だ」 どこかが痛むように軽く眼を伏せたエドワードに、ロイは違う、と呟く。エドワードが怪訝そうに目を上げた。 「何が?」 「死ばかりが別れではない」 ゆっくりと瞬いたその目が、まさに母を連想したのだと告げている。 ロイはかぶりを振った。 「そういうことではないんだ。……私は私の道を歩むために君が邪魔になれば、躊躇わず君を切り捨てる」 「─────」 「犬猫ですら最後まで面倒を見ることが出来ないのに拾ってやるのは酷だ」 その命の尽きるまで、その気持ちの尽きるまで握っていてやれないのなら、いっそ繋がぬほうがいい。 「………君にしがらみを背負わせたくはなかったんだ」 縛りたくないから、と以前言われた言葉をエドワードは思い出した。 告げれば縛られてしまうから、と。言葉とは言霊であるのだと。 決して口にはしなかった言葉を、どうしてもと強請ったのは、オレだ。 優しい沈黙を破らせたのはオレだ。 (………だから) 「いいよ、気にすんな」 軽い口調に俯いていたロイが目を上げた。エドワードはにっと笑って見せる。 「アンタの気持ち聞けただけで充分。すげぇ嬉しい。アンタの未来までは求めないから安心しろよ。付き合える間は付き合ってくれんだろ? それでいいよ。アンタの都合の許す限りで」 そもそもオレだってオレの都合でアンタを振り回してんだし。 「……オレはずっとアンタを好きだと思うけど、アンタにそうしろって言ってるわけじゃないよ」 「鋼の」 「アンタちょっと馬鹿だよな。なんでそういうとこだけ誠実なんだよ。気持ちに応えるっていうのは別に、永久にそうであることを誓うわけじゃないってことくらいはオレにも解るよ」 エドワードは握った手をゆっくりと持ち上げ、祈るように跪くように、額へと押し当てた。 「なあ、大佐。結婚式でどうしてカミサマに誓うか知っているか」 「………え?」 「決して裏切れない相手へ誓うことで、がんじがらめになるためだよ。そうやって何かに縛られていないと心は変わるもんなんだそうだ」 「心が変わりやすいものだというのは同感だが、その考え方はあまりに厭世的だな」 そうかな、と小さく笑って額から手を離し、エドワードはその骨張った男の指に口付けた。 「オレは決して心変わりはしないしカミサマも信じちゃいないけど」 「…………」 「それでも、誓う。………アルフォンスの名前に誓う。アンタが好きだ」 ほんの僅かに怯えるように、掴んだ手が強ばった。その引きかけた手を逃がさず、エドワードは瞳を上げる。恋人は無表情でいたが、穴のような眼に映るエドワードの鏡像が微かに揺らいだ。 にや、と悪戯の成功した子供のような笑みを浮かべ、エドワードはもう一度、視線を合わせたまま今度は意図して薬指を狙い、口付けた。 「左手の薬指は勘弁しといてやるよ。アンタを縛るつもりはないからな」 「………やれやれ」 ロイは天井を仰いで呆れたように短く嘆息した。 「まったく、相変わらずこちらの気持ちなどお構いなしなんだな、君は」 「オレらしいだろ」 手の中からするりと逃げた右手がこつ、と軽く額を叩く。 「開き直るな」 エドワードは額を抑えて笑い、肩を竦めて立ち上がったロイに続いて立ち本を抱えた。 「アンタんち行っていい?」 「アルフォンス君に頼まれたからな」 「……そういや、アルと何話したんだよ」 重ねたファイルを棚に戻していたロイがふと手を止め中空を見つめ考え込んだ。しかしすぐに作業を再開する。 「なあ」 「秘密だ」 「何それ」 見下ろした黒い眼が意地悪く笑っている。 「あんまり色々と一気に明かして君の興味が離れてしまったらつまらないからな」 「うわ、何、さっき言ったこと全然信じてねーの?」 「信じるも何も、未来のことなど誰にも解りはしないさ。それこそ神でもなければ」 言って、ふと口を噤んだロイはひとつ瞬いて再び口を開いた。 「なあ、鋼の。さっきの話だが」 「どれ」 「結婚式でうんぬんというヤツだ。私はあれは、死が二人を分かつまで、と誓った者たちの遠い未来に別れる運命があったとして、どうぞその運命を曲げこの身尽きるまで共に行かせてくださいと神に願うものだと聞いたことがある」 「うわ、なんか少女趣味っつーか」 「まあ、女性好きしそうな解釈だとは思う」 「それ女に聞いたんだろ」 「さあ、どうだったかな」 ふふふ、と笑ったロイにエドワードは軽く舌打ちをする。 「ちょっとは女遊び控えたら?」 「何を言う、遊びじゃないぞ。かなり真剣に恋愛しているんだ」 「何人とだよ……」 もう一度舌打ちし、エドワードは爪先立ちでロイの首へと腕を絡め、体重を掛けて頭を引き寄せぺろりと色の悪い唇を舐めた。ロイは眉を顰める。 「………あのな、鋼の。ここは職場で」 「解ってるよ。だから続きはアンタんちで」 途端半眼になったロイが嫌そうにエドワードを見る。 「大人しく書斎を見ていては……」 「んなわけねーだろ」 はあ、と溜息を吐き、まだ首に絡んでいる腕を掴んで解かせ、ロイは半分諦めたような顔をした。 「まったく、子供のお守りは疲れるよ」 「そこが可愛いとか思ってるくせに」 くっ、と思わず笑ったロイは、自信満々な顔をしている小さな錬金術師の瞼に子供の舌で濡らされたばかりの唇を付けた。 唇に金色の睫が微かに触れた。 |
1<<
■2004/7/14 なにこの話。
どうしてこんな乙女な展開になっているのか自分でも解らず途中で投げ出したくなること数知れず。しかしとりあえず歯車からの一連の話はこれで終わります。そしてまた頭悪いエドロイに戻ります。エドロイはアホで!(コンセプト)
…いえ、この話も相当にアホだと思いますが。何ってわたしの頭が。どうでもいいぷち雑学。名無し指は薬指のこと。薬指は魔法の指ゆえ名を明かしてはならず、魔法の指ゆえ医師はこの指で薬を塗ったのだそう。左手の薬指は西洋では指輪の指。誓うための指であるのはやはり魔法の指で神に近いからなんでしょう。
なんつってー。普段使わない清潔な指だからこの指で薬を塗っていたという説もあるのでほんとだかどうだかは解りませんが、まあここからタイトルとりました。
■NOVELTOP