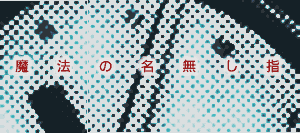
傷 に 滲 み 入 る 薬 を 塗 る
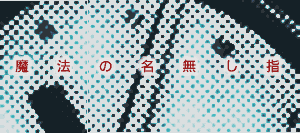
|
かさ、とページを捲る音で気が付いた。顔を上げる間にも耳にはさらさらと紙にペンを走らせる音が届いている。 頭を巡らせるまでもなくすぐ正面に座り脇にファイルを積み上げ何か書き込んでいた上官に、エドワードは一瞬思考が止まりそのままの姿勢で固まった。 「おかえり」 「へ?」 ぱら、とどうやらスクラップブックらしいファイルを片手で捲りながら目も上げずにそう言ったロイに、エドワードは思わず胸に抱いていた本を下ろしながら泳ぐ目を向ける。 「な、なに……?」 「だから、おかえり」 「って、オレずっとここにいたんだけど」 「活字の世界に出掛けてしまって呼んでも戻って来なかっただろうが」 「………呼んだの」 ロイはようやく顔を上げ、どことなく不機嫌を滲ませた顔で眉を寄せた。 「声も掛けずに正面に座って書類を広げているほうが変だろう」 「そ、それはそうだけど……って、今、何時。アルは」 ロイは手にした万年筆で壁に掛かる時計を差した。 「もうじき10時だ、当然夜の。アルフォンス君は昼の内に図書館の閲禁書架の閲覧許可が降りて出掛けた。そのまま宿に戻ると言っていたが」 「んじゃ、もう帰ったのか」 「伝言がある」 じゃあオレも、と目を合わせずにそそくさと立ち上がろうとしたエドワードはぱちり、と万年筆を置いた音とそのよく通る声に動きを止める。 「伝言……?」 「アルフォンス君は明日も朝から図書館に籠もるから、君はこの資料室を読み尽くして来いと」 「って、それは帰ってこなくていいから徹夜でなんとかしろってことかよ」 「馬鹿者。もう10時だと言ったろうが。君のここの閲覧許可は8時で切れている」 「あ、そっか……って、え、あれ、じゃあなんでオレ追い出されてないの」 「事務には私が出るときに連れて出るからと言っておいた」 深々と溜息を吐き、ロイは不機嫌なままファイルを閉じた。 「まったく、君のおかげで中尉の見舞いにも行けなかった」 「なんでオレのせいだよ、追い出せばよかったろ。てか、中尉どうかしたの」 「風邪で熱が下がらないようでね、今日は休んでいるんだ。帰りに寄って食料品を届けるついでに犬の世話をする予定だったんだが」 「って、女の人がひとりで寝てるとこに、アンタが?」 「私なら鍵を持っているから起こさずに済ませてこれるからな」 「なんで鍵!?」 がた、と音を立てて立ち上がり身を乗り出したエドワードにロイはにやりと笑って見せた。 「信用されていて羨ましいだろう」 「いやいやいや、有り得ねェ! 女の人いないの他に!?」 「生憎鍵を預けられるほどの女友達は士官の中にはいないようだよ。そもそも東方司令部は女性士官はほとんどいないしな。彼女は官舎に住んでいるから、下官に鍵を預けでもすると憲兵に咎められたときに相手が困る」 「でも、なんでよりにもよってアンタ」 「だから信用されているんだと言うのに」 「どこが」 「………君は何か私を誤解している……」 はー、と溜息を吐き、ロイは指を組んで肘を突いた。 「ま、ハボック少尉とフュリー曹長が寄ると言っていたから、犬が飢え死にすることはないだろう。あいつらに病人食を選べるとは思えないが、薬くらいは届けられるだろうし」 「……中尉そんなに酷いの」 「昨日は無理矢理医務室送りにしたら、直ぐに病院送りにされて点滴を受けてハボック少尉に送られて帰ったようだよ。彼女はちょっと自分の限界点を高く設定し過ぎなんだ」 「アンタは低過ぎ」 「失礼だな君は」 軽口にへへ、とわずかに笑い、エドワードは蹴飛ばしてしまった椅子を戻して座った。 「ほんとに追い出してくれりゃあよかったのに。悪かったな」 答えず、皮肉げに唇を曲げて再び万年筆を手にしたロイをエドワードは頬杖を突いて眺めた。こめかみの痣は白いガーゼに綺麗に隠されてしまっているが、左目には充血の跡が残る。凝固した血はしばらくは眼球から抜けはしないだろう。 エドワードははわずかに目を伏せた。 「………アンタは? まだ仕事?」 「いや、もう終わりだ。今日の分はとっくに終わっているし」 「……じゃあなんで帰んねーの」 「君を持ち帰らねばならんからな」 「は?」 きょとんと目を丸くしてそれから一瞬頬を弛ませ、すぐに強ばったエドワードの顔を見てロイはくるりと指の上で万年筆を回した。 「百面相」 「るせぇ。何でオレを……」 「アルフォンス君からもうひとつ伝言だ」 「分けて言うなよ」 ロイは僅かに首を傾げた。口元には面白がるような笑みが漂っているが、黒い眼には笑みの欠片もない。 「今日確認できなかった分、私のところの書斎も読み尽くして来いと」 ───アルのヤツ! 胸の中で弟に毒突き、エドワードは眉を顰めて溜息を吐いた。 「確かに伝えたぞ」 「んなこと言われたって……アンタだって迷惑だろ」 「今更何を言っているんだ。迷惑ならもう充分掛けられている」 「………悪かったな!」 ふ、と今度は瞳を弛ませて僅かに笑い、ロイは開いていたファイルを閉じた。 「……私はアルフォンス君を誤解していたようだ」 唐突な恋人の言葉にエドワードは眉を顰める。 「もっと単純で優しいばかりの存在かと思っていたんだが、私が考えていたよりも遙かに人間らしくて複雑な少年だな。……聡明で強くて狡くて、無垢だ」 「………人間らしいってなんだよ。オレ、アンタってたまにアルのことモノかなんかと間違えてんじゃねえのかって思うんだけど」 「そういうわけではないのだが」 「…………」 ロイの言葉からは嘘は感じられない。だが真偽を嗅ぎ分けることが出来るほどの熱もなく、実際どう考えているのかエドワードには読み取れない。 素直に気に食わないという顔して、エドワードは片足を組みがり、と頭を掻いた。 「ま、いーけどー。アルが人間なのはオレが一番知ってるし、アンタが薄情なのも知ってるしー」 ロイは軽く肩を竦めただけで何も言わず、ファイルを纏め出す。その淡々とした態度にまた少し腹が立つ。 「………あのさ」 「なんだ」 「していい?」 「は?」 立ち上がり机を回り、何を言っているんだこいつは、と心底呆れた顔をしているロイを見下ろして、エドワードはゆっくりと区切るように言葉を継いだ。 「やらして。今、ここで」 「許可すると思っているなら君の頭は相当おかしい」 「……やっぱ駄目か」 言いながら軍服の襟を掴む。ロイは眉を顰めてエドワードをちらりと睨んだが、抵抗しようという気はないようだ。エドワードはふ、とひとつ溜息を吐いて肩を落とした。 「ったく、ちょっとくらい嫌がるとか怖がるとかしろよ」 「おや、伝わっていなかったのか。心底嫌だ。怖くはないが」 「へー、怖くないんだ。言っとくけど発火布嵌める暇はねーよ」 「銃をぶっ放す暇はあるんじゃないか?」 「アンタの首が落ちるほうが早いだろ」 「君には出来ない」 「……出来ないと思いたい、の間違いじゃないの」 ふとロイが黙る。その無言につられたように僅かに混乱して、エドワードは襟を掴んだ手に力を込めてロイを椅子ごと引き倒した。うわ、と緊張感のない声を上げたロイは僅かに受け身を取ったようだが、それでも強く背を打ち顔を顰める。 「痛いじゃないか」 「これで痛くなかったら身体おかしいよ。良かったな、正常で」 即座に馬乗りになり両手で胸倉を掴み上げて上体を浮かばせ、口付けようとすると大きな手に阻まれた。 エドワードは舌打ちをしてまだボタンを外してもいない襟元の僅かに覗く膚に唇を落とす。ロイからの抵抗はない。そのままボタンを二つ外し、鎖骨に軽く歯を立てて見たが、やはり何の反応もない。 顔を上げて見ると、ロイは先ほどキスの邪魔をした左腕を枕代わりに頭の下へと敷き、どことなく面白がるような目でエドワードを見下ろしていた。 「………おい」 「なんだ」 「嫌がるとかなんとかしろよ!」 「んー」 生返事を返しながら伸びてきた右手がエドワードの肩口から胸を下り腹を通り、色気もなにもない仕草で股間を掴む。エドワードは反射的に飛び起きた。 「ちょ…ッ、何すんだよ!?」 ロイはにやりと人の悪い笑みを浮かべる。 「これだけ萎えてるヤツに襲われたところで抵抗する気にもならんよ」 「うわ凄ぇなめられてんじゃんオレ。無能に不能って言われた」 むかつく、と言い捨てエドワードは再びロイにのし掛かり頬の横へと両手を突いた。 「ぜってー犯す! 困らせてやる」 「うーん」 左腕の枕はそのままに、ロイはちらりと壁の時計へと視線を馳せた。 「あのな、鋼の」 「なんだよ」 「あと2分で見回りが来るからどいて欲しいんだが、と言っている間にあと1分か」 言葉が終わる前に飛び退き立ち上がったエドワードに、ロイはくつくつと喉を鳴らして笑った。 「本当に困らせたいのなら絶好のチャンスだろうに」 「───なんだよ嘘かよ!!」 ロイは笑いながら身を起こし、埃を払ってボタンを留め、倒れていた椅子を起こして腰掛けた。 「おい、嘘なんだな」 髪を撫で付けながらロイは唇へと人差し指を当て、顎をしゃくり扉を示す。澄ました耳に軍靴の踵がこつこつと廊下を叩く音が届き、程なくして扉が開いた。 「あれ、大佐。まだお帰りではなかったんですか」 「ああ、ちょっと調べものがね」 「そりゃご苦労様です。……で、えーと、鋼の錬金術師殿は」 「私が帰るときには連れて出るからと事務には言ってある」 「そうですか。では鍵のほうも」 ロイは右手を持ち上げた。その指には先ほどまでたしかにエドワードのポケットに収まっていたはずの、資料室の鍵がぶら下がっている。 「私が掛けて行くから構わんよ」 「イエッサ。んじゃ、ホークアイ中尉が復帰したら大佐がどれだけ真面目に仕事してたか伝えておきますんで」 「何を言う。私はいつも真面目に仕事をしているぞ」 「じゃあそう言っていたと中尉に伝えておきます」 「……それは勘弁してくれ」 苦笑いをしたロイとポケットを押さえたまま呆然と立っているエドワードに敬礼をして、上官相手に気安い言葉を交わした下士官は去った。 「……い、いつの間に?」 「さっきしかないだろう」 ポケットを押さえて呟くエドワードにロイはしれっと返した。エドワードはまだ驚愕の表情を落とせぬまま引きつった笑みを浮かべる。 「スリにでもなれんじゃねーのアンタ」 「失敬だな、気付かない君が鈍いんだ。……座りたまえ」 正面の椅子を指差され、それでも突っ立ったままのエドワードにロイは眉を顰める。 「なんだ、続きがしたいとか言い出すんじゃないだろうな。今度は蹴り飛ばすぞ」 「どこをだ」 はー、と溜息を吐いてエドワードはようやく動き、椅子に座った。最初顔を上げたときと同じ距離、同じ位置に戻る。 「鋼の」 「…………。……なに」 ロイはじっと何を考えているか解らない穴のような黒い眼でエドワードを見つめた。 |
>>2
■2004/7/14
■NOVELTOP