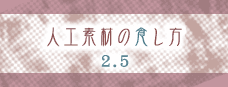
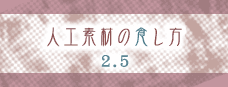
「君が作ったのか?」 食べますか、と差し出されたサンドイッチをひとつつまみながら訊ねると、アルフォンスは「まさか」と笑ってかぶりを振った。 「ボク、料理なんか出来ないです。目玉焼きくらいならなんとか。でもどうしても半熟にならないんですよね」 不思議だなあ、と首を捻る青年にロイは目を瞬かせた。 「では兄が食事を作るのか?」 「兄さんも全然駄目ですよ、料理」 「……では何を食べて暮らしているんだ、君たちは」 「近所のカフェが行き付けです。朝7時からやってるし、夜も11時くらいまで開いてるとこなので」 「外食ばかりか」 「美味しいんですよ? このサンドイッチもそこのです」 ロイは呆れた顔でアルフォンスを眺めた。美味しくないですか、と首を傾げる青年にいや、と返して溜息を吐く。 「料理くらい覚えたらどうだ。難しくはないぞ」 「難しいですよ」 「物凄く美味いものは作れなくても型通りのものなら作れるはずだ。科学者だろう、君たちは。料理は科学だぞ」 アルフォンスは目を瞬かせ、それからああ、と呟いた。 「ハボック大尉が言ってましたけど……そっか、そういう作り方してるから将軍の料理って微妙なんですね」 「なんだ、微妙というのは。というか何を話しているんだあの駄犬」 「美味しくないわけじゃないんだけど物足りないって」 「………後で燃やしておこう」 「や、やめてください、可哀想だから」 「君はあれと仲がいいな」 「将軍のほうが仲がいいじゃないですか」 ロイはにやりと笑う。 「嫉妬かね?」 「………どっちにですか…」 「心配しなくても君のほうが好きだよ。あれは部下だ」 いえ、別に心配はしていないんですけど、そもそも心配する意味が解らない、ていうかどうしてそんな話になるんですか、とぶつぶつと呟くアルフォンスをさらりと流し、ロイはソースの付いた指を舐めた。 「確かに美味いな。どこのカフェだって?」 「あ、ええと、うちのすぐ側の、パンドラってところです」 「災厄の女か」 「……そういう言い方はちょっと」 「今度連れて行ってくれ。兄には内緒で」 「いいですけど……どうして内緒なんですか」 首を傾げるアルフォンスにロイは微笑んだ。女性ならこれで落ちるんだろうなあ、とアルフォンスは呑気に考える。 「殺されるのはごめんだからな」 「…どうしてカフェに行くと兄さんに殺されるんですか」 「君は鈍いのか気付かないふりをしているのか解らないな」 「ボクには将軍が何を言っているのかのほうがよく解りません……」 はあ、と溜息を吐くアルフォンスに声を上げて笑い、ロイは立ち上がった。 「では私は戻るよ」 「お疲れ様です」 「今日は4時で上がりなんだが」 「そうなんですか」 「その後に食事でもどうだ」 「…………。……あの、食事にはちょっと早いと思うんですけど」 「うん。だから、まずお茶をしよう。それから少し散歩をして、夕食を取ればいいだろう」 からかっているんだな、とアルフォンスはふう、と肩を落とした。 「女性を誘ってください。将軍に誘ってもらいたがっている女のひとって何人もいるんですから」 まさか気付いていないなんてことはないでしょう、と首を傾げると、ロイはそれとこれとは別だ、と心外そうに言う。 「つまり今日は駄目だということか」 「遅くなったら兄さんがうるさいので」 「なんだ、今日はあれは非番か。研究所はどうした」 「この間まで忙しかったので明日まで代休です」 そうか、じゃあ仕方がないな、と肩を竦めて、ロイがふと身を屈めた。瞬いている間に顎を掴むように触れた手の親指が、唇の端を拭う。アルフォンスはぽかんと離れて行く手を見、続いてロイを見上げて少し慌てた。 「な、なんですか?」 「パン屑が付いていただけだが?」 何を慌てているのかね、と笑うその顔がにやにやとしていて、ああもう本当にひとが悪い、とアルフォンスは少しむくれた。 「いい加減からかうのはやめてもらえませんか」 「おや、では本気になってもいいのかな」 「何を言っているのかよく解らないんですけど!」 癇癪を起こしかけた青年にはは、と声を上げて笑い、ロイはその短い金髪をさらりと撫でた。 「悪かった、怒るな。では、またな」 ひらりと手を振り姿勢のいい大股で風のように去ってしまった上司に、アルフォンスは深々と溜息を吐いた。 堅い指がまるで羽のように柔らかく触れる。 女たらしの手付きだ、と考えて、アルフォンスは無意識に唇を押さえていたことに気付いた。かあっと耳が熱くなる。 ああもう! これじゃ女の子みたいじゃないか! ぶんぶんとかぶりを振って、アルフォンスは慌てて残りのサンドイッチを頬張った。 |
■2004/9/2 まだ2が出来てないのに幕間が先ってどういうことですか、と思いつつ。自覚があるのかないのか解らないオッサンに振り回されるハタチ。
■NOVELTOP