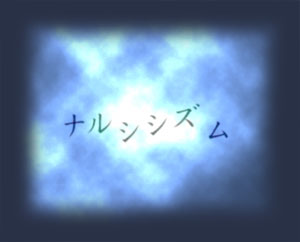
「部下の欲求不満を解消してやるのも上司の仕事だろ」 いやそれは根本的に何かが間違っている何を履き違えているのだこの餓鬼が、と思いはしたが、そう言ってやって彼の神経を逆撫でまた襲われてもたまったものではないので無言で返す。すると無視すんな、と小突かれた。 燃やしてやろうかな。 何をやっても気に喰わないらしいこの青年のその憎たらしい生意気な顔が恐怖に歪む様を想像してみたら気が済んだので、やはり無言で通してぱたりと目を閉じた。 「なあ、アンタさ」 打って変わって甘い口調ですり寄って来た青年の指が、冷えた汗で未だ湿る胸をつう、と辿る。気味が悪いな、と思ったが、黙って目を閉じ続けていると今度は目尻に柔らかな唇が押し付けられた。 肌は荒れ放題で無骨な指などささくれだらけで性交の際も厚い爪があちこちに引っ掛かって堪らなく痛いほどなのに、この青年の唇と髪だけは傷み知らずでいつでも綺麗だ。つややかな髪と唇をやっきになって保っている世の女性が見たら酷く悔しがるのではないだろうか。 何にしてもこの唇だけは好きだ。だからつい吐息を洩らすと、くつくつと喉を鳴らして青年が嗤った。 「散々したのにまだしたいの?」 「………お前は煩い」 頬に伸びて来た手を邪険に払うと髪を掴まれた。薄く眼を開き不機嫌に睨み付ける。途端青年は不安な顔をして手を離した。 「ごめん、痛かった?」 「あちこち痛い。というか気持ちが悪い。吐きそうだ」 「酷ェな」 「どっちが」 青年を押しやり身を起こし、カッターシャツのボタンを留める。ごろりと横たわった青年がそれをぼんやりと見上げていて、その曇った視線が鬱陶しい。 「あのさあ」 「なんだ」 「したいならしていいけど?」 「間に合ってる」 「でもさ」 「お前の自虐に付き合う気はない」 男に突っ込むのは面倒臭いんだ、と言うと、それをアンタが言うのか、と笑われたので横目で見下ろす。 「どうでもいいからさっさと弟を元に戻してそっちといちゃ付け。代替行為に付き合わされるのはうんざりだ」 「何言ってんの。アンタを愛してるから抱くに決まってんじゃん」 「今度弟に会ったら伝えておこう。君の兄は私をあい」 「やめろ殺すぞテメェ」 本気の声だがその両手はまだ頭の下で、この程度の軽口ではこの青年が本当に危害を加えてくることはない。けれど青年の未だ幼年の魂を持ちひとの欲から解放された聖性を保つ弟に本当に告げ口したのなら、迷いなくその両手は打ち合わされ、現れる鋭い刃はこの身を裂く。 その前に燃やせるかな。 彼の身を灼く焔は何色だろう、と想像して、少し楽しくなったので笑う。青年が不審そうに見上げた。 「何笑ってんだよ」 「君を焼き殺したら気分がいいかと思って」 「殺人鬼」 「軍人だからね」 「放火魔」 「君の機械鎧と同じさ」 「一緒にすんな」 ふん、と鼻を鳴らし、けれど再びどんよりと眼を曇らせて、青年は天井を見上げた。 「………アルは性欲の対象じゃない」 戯言を言う。 「アルはそういうんじゃない」 「人間だろう」 「人間でもだ」 「肉体がないからそう錯覚するだけだ」 「肉体があったって同じだ。アルはもっと清い。オレやアンタとは違う」 「その思い込みは彼には迷惑だと思うがね」 青年の眼に昏い光が宿る。 「アンタはアルを解ってない」 どっちが解っていないのか、と思ったが、ただ黙って肩を竦めた。狂信者には何を言っても無駄だ。 「なあ」 「………なんだ」 「またしたいんだけど」 「散々しただろう」 「明日には発つしそしたらまたしばらくは邪魔しねェし、だからいいだろ。たまにのことなんだから」 「旅先で娼婦でも抱けばいいだろう」 「女は駄目だ」 やけにきっぱりと言って、青年は至極真面目に続けた。 「女を抱いたらアルが気付く。アンタなら、アンタんとこに行くと言っておけばアルは素直に報告書を届けに来てるもんだと誤解する」 「迷惑な話だ」 「それに女じゃ万が一妊娠でもさせたとき困るから」 「いいじゃないか、娼婦なら」 「よくねェよ」 青年は歪んだ笑みを浮かべた。 「オレの命はオレ限りだ」 まじまじと青年を見下ろす。金色の眼はガラス玉の中に黄金を閉じ込めたかのようで、生気がない。 身を屈めて青年に覆い被さると、彼の鋼の右手が伸びて来て頭を押さえた。 「………可哀想なヤツだな、君は」 「アンタほどじゃない」 「殺してやろうか」 「そりゃアンタだろ。殺して欲しいなら言えよ」 「………もう一度くらいならしてもいい」 「そりゃどうも」 そういえば性行というものは様々なものの代替行為になり得るのだった、と考えて、自分と彼とはさしずめ殺し合いの代わりなのかな、と思うと酷く可笑しくなったので、声を出して笑った。 頭を押さえて引き寄せた青年が、笑うな、と不機嫌な声を出して唇を塞ぐ。 彼の柔らかな唇だけは好きだ。 焼き殺してしまったらこの唇は無くなってしまうのだな、と思ったので、もう少し彼を生かしておいてやろう、と決めた。 |
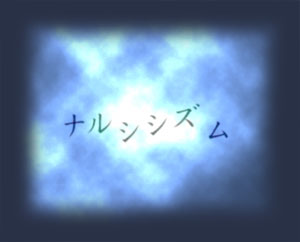
しきりにうなされている青年の唇が、弟の名を呼んだ。縋るように伸ばされた手が空を掻き、酷く歪めた汗だくの顔が少し目障りになり始めていたのでその手を握ってやると、弾かれたように瞼が上がり視線が忙しなく辺りを窺う。 「眼が醒めたかね」 「────ああ、アンタか……」 「うなされるのも結構だが、もう少し静かにやってくれ」 「アルが死んだ夢を見た」 相変わらずひとの話を聞かない。 青年は深く深く息を吐いて、握ったままの手に僅かに力を込めぐいと引き寄せた。その突然の行動について行けず、引かれるままに倒れ込み咄嗟に青年の肩の向こうへと手を突くと皺だらけのシーツが滑った。左手は右手を捉えたまま、青年の鋼の腕がぐるりと首に絡み抱き寄せる。拒むのも面倒でそのまま青年の上へと倒れ込んでやると薄いシャツ越しに早い鼓動が響いた。 「なあ、アンタさ、もしオレより先にアルが死んで、オレが馬鹿なことをしそうになったら、殺してくんないかな」 「馬鹿なこととはなんだ。人体錬成とか、魂の錬成とかそういうことか」 「うん、そう。………アルはそれを望まないかもしれないから」 「望んでいないと何故解る」 「だって今苦しんでる」 無機の身体に、幼いままの心に。 熱に焦がれ狂うこともままならず、いつ失われてしまうのか解らない生に怯え、無機の永久性に怯え。 「それでも生きていたいと言うんだろう、彼は」 「呼び戻せばまたそう言うだろうな。でも、呼び戻されなければそんなことは考えずに済んだって、そうも考えるんだ。言わないけどな」 「言わないのに何故解る」 「解るよ。アルのことなら」 「………………。……解った、ではそのときには止めてやろう」 「殺してくれって」 「死にたいのなら自分で死ね」 は、と青年は嘲るように笑った。 「そりゃそうだ」 「後を追うくらいは出来るんだろう、いくらお前でも」 自己愛の過ぎる、その自己愛を仮初めの生しか持たない幽鬼に投影させている愚かなお前でも。 「あんまりな言い種だ」 「事実だろう」 「アルを侮辱すんな」 「彼を侮辱したわけじゃない」 侮辱するほど興味がない、とは口に出さずに絡む腕を解いて身を起こす。鋼の右腕はずるずると肩を滑り、見下ろした先の金の眼はぼんやりと天井を見上げていた。 「………オレは怖いんだ」 「何が」 「アルが死んで、アルを取り戻そうと死に物狂いになるのも後を追おうと自殺するのも全然怖くない。でももし、狂わなかったらどうしよう」 「……………」 「アルが死んでも平気で飯を食って糞をして眠れる夜が来たらどうしよう。アルにはオレしかいないのに、オレはアルがいなくても平気だったらどうしよう。アルはオレの全てなのに、世界とアルは等価なのに、アルを失っても世界が残ったらどうしよう。こめかみを撃ち抜けなかったらどうしよう両手を打ち合わすことが出来なかったらどうしよう世界が真っ暗でなかったら、それでもオレがオレを赦してしまったら」 「心配しなくても」 震える声でまくし立てる青年の額にそっと掌を当ててみる。青年はすうと気を鎮めその眼が焦点を結んだ。 「そのときには君が躊躇っている引き金を引いて殺してやるし、私が弟を忘れた君を赦さずにいてやろう」 「……………」 「弟が鎧の身体となったのも、お前が毎夜うなされるのも、全部お前が悪いんだ。お前がいなければお前の弟は間違えなかったし、無い生に苦しむこともなかったし、お前さえ寂しさを堪えることが出来たなら───そうでなくとも後を追うことが出来たなら、彼は苦しまずに済んだんだ」 青年はほう、と安堵の息を洩らして僅かに微笑み、生身の指を伸ばした。ささくれた指が首筋を辿る。 「────なあ、アンタ。アンタは殺して欲しかった?」 「ん?」 「中佐が死んだときだよ。…………考えたんだろう、人体錬成」 考えなかったわけがない、とでも言いたげな言葉に軽く片眉を上げて見せると青年はうっすらと笑んだ。 「アンタはオレだ。オレと同じだ。オレにとってアルが不可欠なように、きっとアンタにとってもヒューズ中佐は不可欠だった筈だ。そういう人間がいたはずだ」 「ちらとも考えなかったと言えば嘘だが、私はあれがいなくても生きていける。あれと世界は等価ではない」 「嘘だ」 「本当だ。君にとっての弟と私にとってのあれは違う。────あれはね、化け物なんだよ、鋼の」 「何?」 くつくつと笑って頬杖を突くと青年の視線が追ってくる。僅かに身を起こした青年の掌がシャツ越しに背筋を辿り腰を撫でるのを軽く腕で払うと、金の眼が僅かに不機嫌に細まった。 「大概の人間というものは様々な可能性を秘めていて、どこに生まれどんな教育を受けどんな人間と知り合ったかによってその人生は千差万別だ。私も君も、例えば錬金術師などにならなかった可能性も充分にあった。だがあいつは、決して錬金術師にはなれない生き物だ。そこが君の弟と違う」 「…………頭悪かったの?」 「士官学校時代は私と主席を争うのは最後にはいつもあいつだったよ。そういうことではないんだ。………君の弟は君と同じく生まれながらの錬金術師だが、あれはたとえそうであったとしてもその道は選ばなかっただろう。そういう生き物だ」 「人間じゃないって言ってるように聞こえる」 「人間は完璧ではいられない。無論あれだって完璧ではなかったが、酷く偏ってはいた。あれの懐は底無しで、どんなものでも丸呑みする。どんなときでも屈服せずに健全で闇がなかった。闇のない人間など人間ではない」 善や悪や光や闇や、そのどれもを抱えて人間だ。 「だからね、あれは化け物だったんだよ、鋼。───まあ、君の弟と近いと言えば近いかもしれないな。酷く両極端ではあるが」 「………ああ、」 青年は小さく笑って目を伏せた。 「なんとなく解る、それは」 「だろう」 「うん、普通じゃないんだ」 「私はあれになりたかったんだ、きっと」 「でも絶対になりたくなかったんだろう?」 「そうだな。あれになってしまったらあれと会うことは出来なかったから」 彼が好かれていると自分のことのように嬉しかった。きっと彼を好きな他の人間たちもそう思っていただろう。 「だからね、あれを蘇らせて私の手の内に握ることも後を追うことも、大して意味があることには思えなかったんだ。それでは欠けてしまうだろう。欠けてしまったらあれは普通の人間だ。化け物であったから私はあれが愛しかったのに」 「…………嫌いになるのが怖かった?」 「ああ、怖いね。永久に愛していたいんだ」 「美化されてると思うけど?」 「構わないよ。どうせあいつはもう死んでるんだ」 そうか、と笑って青年は両腕を伸ばした。肩に絡むその腕を今度は拒まずにいると、彼はもう一度笑う。 「今日は優しいな」 「年長者として傷付いた子供を労ろうかと思ってね」 「子供かよ」 「子供だろう」 抱き寄せられるままに身を伏せる。額を肩口に押し付けると、ふうっと髪に息が掛かった。不埒な動きで腰を撫でていた鋼の手がシャツの裾から入り込む。 「────ロイ」 「なんだ」 青年は僅かに身を離し、顔を見つめた。金色の眼が落ち着いた色を見せていて、混乱も悲しみも怒りも狂気も、何も感じさせない醒めた視線が静かに瞬いた。 「もう終わりにしたいんだ」 「………………」 「中佐がアンタにとって神と同じだったように、オレにとってアルは総てだ。世界と等価だ。オレがどうこうしていいものじゃない」 地上に繋ぎ止めていいものじゃない。 青年の柔らかな唇が目尻に触れた。 「アルを殺すかもしれない」 「……………、…………そうか」 「嫌だって言うかもしれないし勝手だって罵られるかもしれないけど」 「だろうな」 「………だから、アンタはオレを殺して」 アルを殺す前にオレを殺して。 「アルのこと、頼むよ。あいつの望む通りにしてやって」 「………君を殺す約束はしたが、君の弟を殺す約束はしていないし、しないぞ」 「うん、いいんだ、オレがそう望んでることだけ憶えといてくれれば」 青年の唇がもう一度、今度は瞼に触れる。 「アルが持って行かれたとき、オレがアンタくらい大人だったらよかったのに」 「………君が私ほどの年だったのなら、そもそも人体錬成などしようとは思わなかったさ」 「それもそうか」 嘘だった。 青年にとっての弟のような存在が在れば、やっていたかもしれなかった。 彼らの罪をこの目で見なければ、親友だって蘇らせようとしたかもしれなかった。 あの怪物をこの手に取り戻そうしなくて良かったと、そう思えるようになったのは本当はつい最近のことなのだ。 けれど多分、この青年はそんなことはお見通しなのだろう。 なんと言っても自分と彼とは酷く似ていて、多分、同じ生き物だ。 「アルを愛してる」 「知ってる」 「アルを愛してる分だけ多分オレはオレを愛してる」 「それも知ってる」 「………アンタはオレだ」 「君は私じゃない」 「オレはオレを愛するように、多分アンタを愛してる」 「傲慢だ」 「知ってたろ?」 「ああ、知ってる」 青年の掌が顎を掴んで唇が塞がれた。僅かに動いたその柔らかな肉が、愛してるよ、と囁いたので、彼を殺す日がそう遠くないことが少しだけ寂しくなった。 自己愛のように彼を愛しているのだと、そう告げてやったら彼は酷く不機嫌になるだろう。 愛されることが嫌いな青年にそうと告げずにいてやることがせめてもの優しさだと思ったので、決して告げずにいてやろうと決めて、そっとこちらから口付けると案の定青年は酷く不機嫌な顔をした。 |
■2005/2/2
前半は随分前に雑記に書いたエドアル前提愛のないエドロイ。後半はその続きでもないけど同じ人たちで同じ設定で少し後、でしょうかね。
特にどうと言うこともないんですが少し書きたくなったので書いてみました、というだけ。別にロイエドでもいい雰囲気ですがロイエドだと多分大佐がちゃんとエドを愛していないと無理だと思いますこの設定。
■NOVELTOP