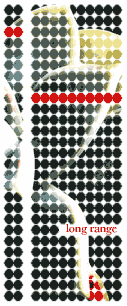
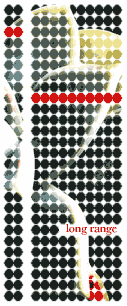
ひとが死んでいるところを見るのは初めてではない。 棺の中に納まったひとがどれだけ綺麗に、またどれだけ生前とは違った表情に見えるかも、清めの手順も、牧師の言葉のひとつひとつも、全部全部覚えている。ただその記憶を手繰るといつでも涙に曇ったファインダーを通した景色しか見えなくて、母が死んだとき、延々と泣き続けてその死に顔をよく見てやれなかったことを今更に少し悔やむ。 そんなことを考えながら棺の中にそっと掴んでいた百合を置いた。額に黒髪が掛かっていて、それが目に入りそうに見えたものだから無意識にそっと鋼の指で払い、その体温のない冷たい膚の感触を掴み損ねたなと考える。けれど左手で触れ直すのも馬鹿馬鹿しい話だと思ったから、黙って一歩退いて、後に続く軍人へと場所を譲った。 「兄さん、兄さん、大佐が」 泣き声を震わせてアルフォンスがエドワードの手を握った。視線が落ち着かず彷徨い、しきりに棺を覗いては首を振る。泣けない弟は今、その魂の内側で零れない涙の熱さに悶えている。冷えない悲しみに身を震わせている。 「兄さん……」 掠れ声がひび割れる。祈るようにエドワードの手に額を付けて身を縮めたアルフォンスを抱き寄せて、エドワードは優しくその鉄の身体を撫でた。 「………行こう、アル」 え、と呟いた弟がエドワードを見つめた。酷く不思議なものでも見るかのような目だった。 「兄さん?」 「オレたちがここにいたって仕方がないだろ。それより次の目的地は北部だ。さっさと行かないと、雪でも降り始めたらもう春まで行けなくなっちまうだろ」 「なに言ってるの?」 小さな悲鳴のような声は非難の色を乗せていて、エドワードは薄く苦笑した。 「だから、オレたちが葬式に出たとこで仕方がないだろって」 「だって、兄さん、大佐だよ? 大佐が死んじゃったんだよ?」 「オレたちの目的のほうが大事だろ。大佐だってそう言うよ。……ああ、でも、お前が葬式に出たいなら、そうしてもいいけど」 「ボクより兄さんだろ!?」 エドワードの心臓は静かに脈打っている。 「オレはいいんだ」 「………どうして!」 「お前が死んだんじゃなくてよかった」 アルフォンスが静かに硬直した。信じられないものでも見たかのような視線は赤々と揺らいでいて、エドワードはそれを見上げ困ったように笑う。 「オレが死んだんじゃなくてよかった」 「兄さ………」 「旅を止めずに済んでよかった」 間違いを繰り返さずに済んだ。 彼を愛していなくて、本当によかった。 ───彼のために命を懸け禁忌を犯す気は、微塵もなかった。 は、と息を吐いてエドワードは瞼を開いた。起き上がり汗のひとつも掻いていない額を拭う。 (………なんつー薄情な夢見てんだオレは) エドワードはまだ朝には遠い時間であることを確認してごろりとベッドにひっくり返った。目を閉じる。ゆっくりと額に汗が浮くのが解る。心臓は加速度的に鼓動を速め酸素を欲して、呼吸が乱れる。 「………大丈夫。あんたが死んだらちゃんと泣く」 今ここにはいない恋人に呟き、エドワードは目を開いた。見上げた先の薄汚れた天井に、明かりを絞ったランプの光が薄く帯を作る。 (けれど足は止めない) あんたもそうしろと言うだろう? 立ち止まり振り向いている暇はないだろうと、───蘇らせるなんて馬鹿なことは考えてくれるなと、多分、そう。 そうだ、きっとそうやって背を押して痛みを削り取ってしまうのだ。 (オレを甘やかしてしまう) せめて息をしやすいようにと、これ以上の罪悪の意識を背負わせまいと。 その生温い庇護を受けている現状にどうしてこれだけ舌が苦く乾くのだろうと考えながら、エドワードはゆっくりと落ち着いてきた鼓動に合わせてゆるゆると戻ってくる眠気のままに瞼を下ろした。毛布がどこかへ行ってしまっていたが、探して身体に掛けるのも面倒でそのまま怠惰に眠りへと降りる。 (………明日には、東部だ) そうしたら久し振りに恋人に会って、そしてこの間のことを謝ろう、とエドワードは眠気に素朴さを増した子供の感情でシンプルに思った。 殺してしまいそうで恐かったのだと素直に言おう。そうして叱ってもらおう。 そうすれば、もう少し。 乾いた舌でも、もう少し楽に息が出来るだろう。 (甘えるのもいい加減にしないと) 早く、大人になって。 誰にも寄り掛からずに済むくらいの。 誰にも噛み付かずに済むくらいの。 誰もがその牙を見ただけで、この腕の中にあるものに手を出す気など失うくらい、強く、大きく。 眠りから醒めればすっかりと忘れてしまう感情を抱え込んだまま、エドワードは深く眠りへと落ちた。 |
■2005/11/13
ごみばこからサルベージしてきました。もと雑記SSS。時間的には水底少し前。スポイルと水底の間あたり。
初出:2005.1.3
■NOVELTOP