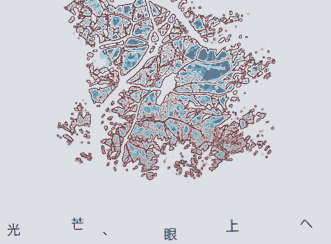
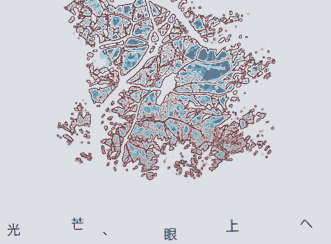
ヅ、ブツン、と、雑音がするのはあちらのせいではなくこちらの回線のせいだ。何もかもが上等とはほど遠い。 『はい。───リザ?』 名乗る前に名を呼ばれてわたしは少し強張った。それから勢い込んではいそうですリザ・ホークアイですお久し振りですご無沙汰してますマスタングさん、と早口でどもりながら言うと、呆気に取られたようにちょっと間を置いてから、電話の向こうであのひとは少し笑った。 『こちらこそ、連絡もせずにすまなかった』 「いいえ! あの、新聞で見て」 あなたが国家資格を取ったことを。 「あの、お祝いを言おうと思って」 『ああ、それは有難う。……新聞には、銘は?』 「え、いえ、」 そうか、と呟くように言って黙ってしまったマスタングさんがなにか言いたげだったから、わたしは黙って待っていた。 『………銘は焔だ。焔の錬金術師、だそうだ』 ふ、と、マスタングさんは自嘲のように笑う。 『師匠に申し訳がないな……結局、私はそう名乗ることは許されないままだったと言うのに』 わたしは少し瞬きをした。このひとが、父さんが結局教えてはくれないままだった秘伝をわたしから掠め取ったように感じていることは薄々気付いてはいたけれど、でもこれほど根深いとは思わなかった。 だって父さんはいつかこのひとに秘伝を教えようとしていたのだし、わたしにその判断を任せたのだから、わたしが選んだ以上、このひとは焔の錬金術師なのだ。 「あの、父は」 わたしはぼそぼそと受話器に向かって囁いた。 「父の弟子はあなただけでしたし、父はわたしに秘伝を託したんです。……わたしはあなたになら教えてもいいと思った。だから、あの」 『うん』 言葉足らずのわたしの言いたいことをきれいに察して、マスタングさんはありがとう、と優しく言った。 『ところで、君は今どこにいるんだ? 前の家に手紙を出したんだが、戻ってしまって』 「あ、前の家は引き払って、今は昔の父の知り合いのところに下宿をさせてもらっているんです」 手紙だなんて! わたしは連絡を取っていなかった自分を殴り付けたくなった。せっかくの手紙を、受け取り損ねたなんて。 『どこに住んでいるんだ? 住所を教えてもらえればまた手紙を……ああ、いや、今度の休暇にでも訪ねに』 「あ、あの! わたし、もうすぐしか……え、ええと」 『ん?』 「あっ、あの、し……しごと、で、寮に入るんです。……あの、とっても遠くて」 だからまたこちらからご連絡します、と緊張に消え入りそうになる声で言うと、マスタングさんは不思議そうにそうか、と相槌を打った。 『では、落ち着くところが決まったらまた連絡を。私は暫くは勤務先は中央のままだし、今年はもう引っ越すこともないと思うから住所も電話番号もこのままだよ』 「は、はい」 多分、もう数年は連絡を取ることはないとは思うけれど。 ───次に会うときには濃紺の、同じ軍服を纏って。 「あの、じゃあ、これで」 もう電話代が掛かりすぎている。この下宿のおばさんはそんなことは気にしないひとだけれど、でも裕福なわけではないのだ。 『うん、では、また。……元気そうでよかった。師匠の墓にも、近いうちに報告に行くよ』 「あ、ありがとうございます……」 挨拶を交わしてちん、と電話をおいて、わたしはほうっ、と大きく息を吐いた。血が頭に上りすぎてくらくらとする気がした。 憶えている通りの、優しい低い声。 「リザちゃん」 ぼんやりと今聞いたばかりの声を反芻していると唐突に声を掛けられて、わたしは飛び上がった。 「あっ、お、おばさん」 「マスタングって、あれだろう。あんたの父さんの弟子だった」 軍人になったんだよねえ、とやれやれと肩を竦めて、おばさんは気遣わしげにわたしを見た。 「………ねえ、リザちゃん。やっぱりやめときなよ、軍学校なんて。あんたの父さんはあんなに軍人嫌いだったのに、弟子だけじゃなく可愛い一人娘まで軍にとられたなんて、浮かばれないよ」 「あの、でも……」 マスタングさんは立派なひとです、と言いたくて、けれど軍人なんて乱暴で女の子がなるもんじゃないんだよ、といつものように始めてしまったおばさんにわたしは困って少し笑う。 でもおばさん、マスタングさんは優しいひとです。とってもいいひとです。頭もよくて、育ちもよくて、これっぽっちも乱暴だなんてことなんかない。 わたしは子供の頃、寄宿学校に入れられていた。暮らすのにも苦労するくらいだったのに、父さんはわたしを学校に入れたがった。それも近所の小学校ではなくて、9年生までの、寄宿学校に。 男の子でもないのに友達とも離れてそんなところに入れられて勉強をさせられて、長期のお休みに帰ってくるたび母さんは痩せて、父さんはいつもの通り全然こちらを見向きもせずに、ずっと書斎で研究を続けていた。 わたしがそのことで不満を漏らすと、母さんは少し笑って、でも父さんは優しくて正しいひとなのよ、と言った。 わたしには全然解らなかった。母さんにこんなに苦労をさせて、働かせて、自分はずっと書斎に籠もっているなんて、錬金術師ってなんてばかなんだろうと思っていた。近所のひとたちがなにか困って頼ってくると何も言わずに壊れたものを直し、知恵を授けてやってはいたからわたしたち家族は疎まれずに済んでいたけれど(このおばさんのように、みんな父さんの味方をするけれど)、でもわたしにはあのひとがいいひとだとはとても思えなかった。 母さんはわたしが10歳のときに、死んだ。お葬式のために夜行列車で戻ったわたしは、お葬式が終わったその夜に父さんの言い付けで夜行列車で学校に戻った。 ゆっくりひとりで泣く間もなかった。 けれど、11歳の新年のお休みに帰ってきたときに父さんの書斎にいたあのひとは、わたしの思っていた錬金術師とは全然違った。 あのひとは15歳か16歳だったけれど、身体もちいさくて近所の同じ年のこどもと比べても全然頼りなかった。でも学校は飛び級をしてもう済ませていて、錬金術を父さんから習っているのだと言った。 あのひとはとびきり頭が良かった。あのひとはとっても優しかった。あのひとは父さんに言われたことを全部こなして全部憶えた。あのひとは父さんをとっても尊敬していた。 父さんが、誰か他人を家に住まわせたのは初めてだった。 けれどわたしが学校を卒業して家に戻ったときには、あのひとは士官学校に入ってしまっていてわたしたちの家には住んではいなかったから、わたしとあのひとはそれほどに親しくなる機会はなかった。 「ね、リザちゃん」 はい、とわたしは顔を上げた。おばさんは渋い顔をして腕を組んだ。 「だからね、やめときなよ、軍人になんかなるのは。父さんが嫌がるよ。だからあんたの母さんだって駆け落ち同然に……」 「え?」 おばさんははた、と口を閉じ、それからううんなんでも、だからね、軍人はね、と慌てて誤魔化してしまった。 「あんたみたいな可愛い子のなるもんじゃないよ。あんたせっかくちゃんとした学校も出てるのに。軍なんかね、他に取り柄がなくって嫁の貰い手もないようなばかが入るもんなんだよ」 極論に、わたしは思わず笑ってしまった。このおばさんの二人目の娘さんは、おばさんの反対を押し切って軍学校に入った、今第一線で働く軍人なのだ。わたしは何度か会ったことがあったけれど、とっても美人で快活で気持ちのいい女の人だ。ただ、もう三十になるのに結婚する素振りがこれっぽっちもないことが、おばさんにはさみしいんだろうと思う。 おばさんの一人目の娘さんは南にお嫁に行ったけれど、国境の小競り合いが少しこじれたときに巻き込まれて、旦那さん共々亡くなっていた。 「大丈夫よ、おばさん」 わたしは胸を叩いて見せた。 「わたしこれでも学校の体育はとっても成績がよかったの。走るのだって誰より早かったし、泳ぎも上手いのよ。遠泳の選手にだってなったことあるんだから」 「あのね、リザちゃん。駆けっこや水泳が上手くたって」 「もちろんそうだけど、運動が出来ることは軍人には大事じゃない?」 でもね、とまだ引き留めたそうなおばさんは、きっと納得してくれることはないんだと思う。けれどわたしはどうしても、この戦いの多い国を、そこに住むひとたちを助けたいと思った。おばさんの一番上の娘さんとその旦那さんが亡くなって、そうして二番目の娘さんが軍学校に飛び込んでしまったみたいに、罪もないひとが戦火に焼かれる、そんなおかしなことをなくしたかった。 あのひとの理想はとてもとてもきれいで絵空事で、でも、夢見るひとが夢を叶える力を持てば、きっといつか叶うような気がした。 あのひとは名実共に焔の錬金術師となって、そうして一歩夢に近付いた。 同じ夢を見たくなってしまったわたしは、その後を追い掛けたいのだ。 「おばさん、ね、そろそろご飯の準備をしなくちゃ。わたし手伝うから」 はあ、とおばさんは溜息を吐いて、そうだね、と頷いて階段の下からどいてくれたので、わたしはようやく二段上の電話の置いてある踊り場から出ることが出来た。 ちょっと振り向いて、古い電話を見る。 ここから、あのひとに電話をすることなんてもうないけど。 次に会うときは濃紺の、同じ軍服を纏って。 ───血の煙る、戦場で。 |
■2006/8/8
感想文SSにしようかとも思ったんですがなんとなくこっちに。
憧れと恋と無意識のファザコンがごっちゃのロイ←アイ。
■NOVELTOP