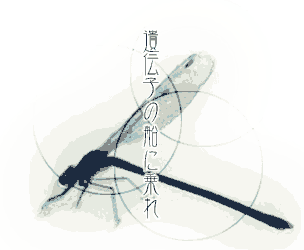
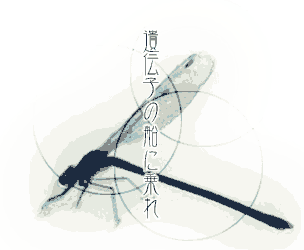
彩度の低い夢を見ているな、と思った。 夢の中で狭くもないが屋敷と呼ぶにはささやかな家の廊下を歩きながら、ひとつひとつ開けていく扉は己の思う通りにバスルームで、居間で、キッチンで、客間で、このしっくり馴染む配置を見るに、いつかこの家に住むことがあるのかもしれないとロイは思う。ふわふわと頼りのない感覚で歩きながら、己のためにしつらえたかのような家の階段をゆっくりと上る。 寝室がふたつ。屋根裏への階段が、ひとつ。納戸がひとつ、空き部屋がひとつ。 ここは書斎だな、と、窓の明かりを半分だけ斜めに掛けた奥まった扉の前に立ち、ひやりと冷たいノブを握ってゆっくりと重い扉を開くと、音もなく光が溢れた。 実際には窓には鎧戸が半ば以上降りていて、そうでなくても窓の外に掛けられた侵入者避けの鉄格子に絡まった蔦が日光を遮っていて薄暗いのに、その金色の髪が彩度の低い世界になれた目に鮮やかだ。 広い──肩。流した金の長髪は首の後ろでひとつにくくられ、広い背中を少し丸めるようにして机に座った人物は、かりかりとペンを走らせ何を書いているようだ。 ふいに、ぴたりと脇から覗いていたペンの先が止まった。 「………ロイ?」 顔も上げず、思案げにペンを口元へと寄せて囁いた声色はバステノールで、さほど低音ではないというのに不思議と腹に響くように紡がれる。 その低音が、再びかりかりと紙をペン先で引っ掻きながら続けた。 「もうちょっとだから待ってろ。───予約は何時だっけ? まだ平気だろ? アルから催促の電話でも来たか?」 この背中にも声にも、まるで覚えはない。 けれどその鮮やかに濃い、金髪の色が。 稲穂よりも黄味が強く、オレンジよりも褐色じみた。 太陽と黄金の。 「ロイ?」 なんとか言えよ、と振り向いた男は、意志の強そうな眉の下の鋭い金の瞳を薄いレンズの奥でぱちり、と瞬かせた。 三十代半ば、と言うところだろうか。太く真っ直ぐな鼻梁に、がっしりとした顎。薄い唇の大きな口は今はわずかにぽかんと開かれている。長い前髪に彩られる頬はけれどやわらかなラインなどとは縁遠く、それから続くがっしりとした首には筋肉の筋が浮いた。 着古したかのような皺だらけのシャツから覗くその右手は鋼で、その無機を持ち上げて男はしっかりとした顎を撫でた。 「────、『大佐』、か?」 ロイはただ男を凝視した。貴方は誰だ、と問うべきか───貴様は何者だ、と誰何するべきか。 それとも、君───と、呼ぶに相応しいのか。 沈黙するロイに構わず男はふっと笑うと眼鏡を抜き、立ち上がった。姿勢のいい、少し乱暴な歩き方でロイに近付くその姿は表情や纏う雰囲気によって一回りも二回りも大きく見えてはいたが、実際にはロイとさほど変わりのない身長のようだ。男のほうが幾分か視線が高いが、それでも金髪に白い膚の人種としては小柄とは言えないまでも大きなほうではないだろう。 近付くと、その膚が日に焼けて少し荒れているのが見て取れた。剥がれ切らない瘡蓋が左頬にこびりついている。 「ロイ? どうしたんだ、ぼうっとして。オレに見蕩れた?」 「────何者だ」 「『鋼の』さ」 くつくつと笑い、男は一見柔らかな光を乗せた金の眼で黒眼を覗き込む。鋭い眼が笑みに弧を描いた。 「軍服………ああ、やっぱり大佐なんだな。いつのロイなんだろう? まだ二十代?」 「…………」 「何か言えよ、相変わらず突発事項に弱いな。訊きたいことは?」 馴れ馴れしい仕種に、ロイは眉間の皺を深くする。 「名を呼ぶのか」 「ああ、」 男は苦笑した。 「呼ぶよ。オレは軍属じゃないからな、ロイの部下じゃないんだ。階級で呼ぶ必要も敬礼を返す必要もない」 「………軍属ではないのか?」 「随分と前に銀時計は返したよ。───ほら、来いよ」 ふいに無機の右手に手首が掴まれ、その無遠慮な仕種に抗議する間もなくぐいと引かれる。男はロイの手首をしっかりと握ったまま、書斎机の引き出しを開けたり閉めたりしながら何かを探している様子だ。 「ああ、ほらほら、これ」 ぺらり、と翳して見せた端の黄ばんだ薄い紙は、確かに国家錬金術師資格の剥奪書だ。 「………平穏無事に返却したのではないのか」 「事情があって査定出来なかったんだ、2年続けて」 「研究費の返還を、」 「求められたよ。使ってなかったからまるまる返した」 「刑罰が」 「あったよ。刑期1年で、模範囚で半年で出た」 軽罪の囚人ばっかだったからのんびりしてる刑務所だった、と笑い、男は手首を離して鋼の手にやんわりとロイの手を包み、温かな左手でぽんぽん、と軽くあやすように叩いた。 「ま、後ろ盾があったからな。フツーにしてただけだけど、すぐ出られたよ。面白い経験だった」 ロイは無言で、手を包む鋼の指をそっと握る。 「………機械鎧のままだ」 「うん」 男は微かに眼を細めた。 「左脚と、アル……どうなったか、知りたい?」 「先程アルフォンスから電話が、と」 「うん、生きてるよ、アルもちゃんと。元に戻れたかどうか、知りたいか? アンタが今なにをしているのかとか……世の中が、どう変わっているのかとか」 ロイは男の眼を見つめる。静かに、けれどその中心に強固で揺るぎない意志を宿すその硬質な眼は、ロイの答えを知っているようだった。 この男はロイを知りすぎている。その上で、まるで試すように───甘やかすように、そうして甘く提示するのだ。 ───未来、を。 「………夢を見ているからな」 「うん?」 「夢の中で未来を訊いたところで、現れるのは私の願望か、その裏返しに過ぎないだろう」 「じゃあ、訊いとく?」 「いや、」 ロイはゆるくかぶりを振った。 「遠慮しよう。………望む未来であろうとそうでなかろうと、知ることで枷になれば、困る」 「相変わらず言霊を信じているんだな」 喉を鳴らして笑い、男は薄紙をしまった引き出しを閉じ、荒れた皮の厚い左の人差し指でロイの頬を撫でた。その触れるか触れないかといった性的な含みのない、けれど成人男性にするには甘い仕種に不思議と嫌悪はなくて、ロイはひとつ瞬いた。 「………そろそろ帰る時間じゃないか、ロイ」 右手をポケットに突っ込み、握り締めた左手を下ろして男は微笑む。ロイはもう一度瞬いて、何を思うでもなくただ頷いた。操り人形のような己の仕種に疑問を挟む余地もなく、勝手に踵が返される。 それほど広くもない書斎を横切り開きっぱなしだった扉の敷居を踏んで、廊下に半歩出たところで背後に気配が増した。 「ロイ」 ぐっと肘を掴み耳許に寄せられた唇が、熱く低く囁く。 「───愛してるよ」 忘れないで。 その息の温度と陳腐な言葉と声色に込められた恐ろしく似合わない慈しみの気配に、ぎょっとして振り向くともうそこに男はいなかった。 ロイは何度か瞬いて、見慣れた仮眠室の天井を見上げる。 「………変な夢を見たな」 本日午後の列車でこちらへ寄ると連絡のあったあの子供に、この夢を話してやったとすれば。 多分えらく喜ぶんだろうなあ、とうんざりとして、ロイは誰にも話さずただ記憶の奥へと押し遣ることに決めて、じり、と鳴りかけた目覚まし時計をばしんと叩いて止めた。 「なあ、大佐」 うつらうつらと眠り掛けている隣の男に囁くと、なんだ、と寝惚けた声が答えた。薄い夜着を纏う、大して熱くなることをしない表皮のひやりと冷えた身体にそっと掛け布を引き上げて、エドワードは囁く。 「今日、大佐に会ったよ」 「………もう少し私に解る言葉で話してくれないか」 「若かったなー。アンタ若作りだと思ってたけど、やっぱこう……膚のカンジとかさー、違うよな」 「若い男に走りたいならそうしろ。この年で君の相手も疲れるんだ」 「なんでオレがアンタ以外の男に走んなきゃねえの」 「いやそもそも男に走るのがなあ……」 「あーうるさい、そういう話したいんじゃなくて」 頬に掛けられた手に促され、億劫そうに薄い瞼が持ち上がる。かつては炯々と光った黒い眼は僅かに色を落とし灰色掛かって、その古びた毛布のような闇が、酷く優しくあたたかい。 そっと髪を梳くと指に絡まる細い黒髪に、幾筋か銀色のものが混じる。ランプの光にきらきらとするそれを丁寧に梳きながら、エドワードは再び瞼を閉じてしまった男を眼を細めて見つめた。 「レストランに行く前にオレ、書斎に篭もってたろう? そのときにね」 「うたた寝でもしていたのか」 「ああ、そうかもな」 くつくつと喉を鳴らして笑い、エドワードはぼふ、と枕に側頭部を付けた。目の前に眼を閉じた見慣れた顔がある。 「若いアンタはかわいかったよ。なんか、こう、理想の高いカンジがさ」 「純粋で真面目で繊細だったんだ。なのに15のクソガキに振り回されて、君に見えないところでどれだけ私が傷付いていたか」 「図太くて鈍くて横柄だったくせになに言ってんだ」 鈍くて、どれだけ自分がこの男を好きでいたのかそんなことにも気付かずに、───自身が、どれほどあの金髪の子供を目映く思っていたのかそれにすら気付かずにいた、若く理想の高い、己の規範をいなし従う術をまだ知らずにいた頃の。 「あれがこれになるのかと思ったら」 「がっかりしたか?」 「いや、凄く愛しいなあと」 「臆面もないというのは君のことを言うのだろうな」 「………アンタに息子がいたらあんなのだったかなあ」 うっすらと開いた黒い眼が、軽く嘆息してエドワードの鼻先をぎゅ、と握った。 「選んだのは君で私だ。どちらか一方の責任で成り立っている関係ではないだろう。余計なことを考えていないで、もう寝ろ」 「でもさ」 「明日は早いんだろう……明日の列車を逃せば次は半年経たなければシンには行けないぞ。アルフォンスに置いて行かれたいのか?」 どうしてそんなにギリギリのスケジュールを組むんだ、と再び嘆息した男にだってさ、と子供のように唇を尖らせて、その尖らせたままの唇でエドワードは軽く口付けた。 「アンタと出来るだけ長く一緒にいたかったんだもん」 「そうかそうか、それは光栄だ。もう充分堪能したろう」 だから寝ろ、と命じる命令しなれた声に了解、と返して、エドワードは眼を閉じた。瞼に触れていた金髪を、かさついた指先がそっと掻き上げる。 「…………、……鋼の?」 「んー?」 酷く慈しみの強い低い声が、柔らかに囁いた。 「もし君が旅の途中で息子や娘を得たいと思ったら、戻る必要はないんだからな」 反射的に開いた瞼の向こうで、もうじき五十路に手の届く男がどこか悪戯でも企むような微笑を浮かべている。その子供のような微笑の裏に強い慈しみと親愛を感じて、エドワードは眉を顰めた。 「馬鹿言うな」 「馬鹿じゃないさ。………君が若い私の未来に負い目を感じたというのなら解るだろう。私は君の子供が見たいとも思うんだ。君が、どんな女性を選んで、」 その血が、どこへ繋がって行くのかを。 「………私から見れば君はまだ若い。いくらでも未来を掴んで行ける。今のまま、これで終わりではないよ」 「……………」 「……だが、願わくば」 ふ、と、はにかむように視線が伏せられた。 「戻る必要はないが、一言───手紙でも電話でも、戻らない旨を伝えてくれると有難い」 戻らない者をそれを承知で待つことと、いつか戻るかと望みを掛けて待つことは、似ているようでまるで違う。 「………戻らないのに、待つのか?」 「年を取ると、そういうことが平気になっていくものなんだ」 もう戻らないと、戻ることなど望みもしないとそう思っていても。 それでもいつでも愛し子が、疲れた羽を休めに傷付いた魂を癒しに舞い戻れるように。 その寝床を、設えてやれるように。 「じじいくさいぞ、それ」 「じじいだろう、君から見れば、充分」 息子より孫が似合う年じゃないか、とくつくつと笑った黒髪にそっと掌を滑らせて、エドワードは口元に笑みを掃いた。 「まあ、ないとは思うけどもし運命的な出会いなんてもんに遭遇しちゃったときには、ちゃんと知らせるよ」 「そうしてくれ」 「オレの運命の相手はアンタだと嬉しいんだけど」 「………そこで突っかからなくなっただけでも随分大人になったな、君も」 「いやそれがじじいくさいんだって」 オレも三十五だぜ、もう、と笑って、エドワードはそっと白髪交じりの髪の掛かる額へと口付けた。 「愛してるよ、ロイ」 「………おやすみ、鋼の」 「おやすみ」 もう一度羽が触れるように口付けて、エドワードはゆっくりと眼を閉じた。 |
■2006/1/18
JUNKにある『fall fall fall』の逆verというお題をいただいて書いてみたらオッサン×オッサンまでおまけについたという。35×29はなんか凄い自分の中でもやもやとして耐えられなくなって書き切れなかったです考察が足りなかった…。
ところでシャレードと設定が違うのでびみょーにSSエドロイとは軸がズレてる感じです。ひとは同じだと思いますが。
ちゃんとした逆verの29×29はまたそのうちなにかで書きたいと思います。初出:2006.1.8
■NOVELTOP